「SQLite for Excel」 Excel VBAからSQLiteデータベースを使用する SQLポケリ [SQLポケリ]
えーと本日は、SQLiteネタである。
Webアプリ全盛な時代なのに、現場ではExcel使ってデータ入力したり、帳票出力するっていうところがいまだに多いようである。特に、街の小さな工場とか、商店とか。
Oracleデータベース使って、Webサーバと連携して、JavaScriptでリッチなクライアントを作成して、というのが流行りではあるものの「それはIT業界に限った話」でしかないのかも。
そもそも、小さな工場ならデータベースを使ったシステムなんか要らないのかも。
しかし、どういうわけか「現場の人はExcel好き」だったりする。ExcelのVLOOKUPやMATCH+INDEXじゃあパフォーマンス的に限界があるから、データベースに移行してくださいよ。といってもなかなか受け入れてもらえなかったりする。
普通にシステムを作成していても、Excelシートでデータを見たいんだけど...っていう要望が多かったり...
なぜか?
VBAが苦手。ましてやSQLなんて意味不明。Excel関数でできるじゃん。
という人が多いのであろう。
Excel使っているのなら、Access入れれば結構いい感じのシステムになりそうなのに。なんでイマドキMATCHやらINDEXとかのExcel関数使うのよ。もう。
Officeのプロフェッショナルは高い
Accessは、別に買わないといけない。
Excel、Word、OutlookはOfficeのセットなのだが、ここにAccessが入っていないので、高い方のOfficeを買わないといけない。それがネックなのか...

MS Accessの記事についてはこちらを参照されたし
じゃあ、SQL Server Express入れてしまえばいいじゃん。と思うのだが、これはシステム屋が考えることらしい。無料で使えるといっても、データベースサーバを導入することについては「敷居が高い」と思われている。
うーん。まぁねぇ。専用のサーバマシンを導入したくなるし、運用面を考えるとなぁ...
MySQLやPostgreSQLという線もあるのではあるが、こっちは一層敷居が高くなってしまう。
データベースサーバを入れたら、複数のユーザで使えるようなシステムにできるので、かなり効率アップできると思うのだが...
ちょっと話を整理する
Accessを買うのがもったいない
別にデータベースサーバが欲しいわけじゃない
ちょっと遅いけどExcelで十分じゃない
ということなのかも知れない。
じゃあ、Excel+SQLiteで万事うまくいくのでは?
そう思っている人も多いらしく「SQLite for Excel」というパッケージが存在する。
ExcelからSQLiteを使うときは、SQLiteのODBCドライバを入れる方法もある。
SQLite ODBCの記事
今回は、SQLite for Excelをやってみたい。
SQLite for Excelは以下のURLからダウンロードできる
SQLite for Excel
GitHubってよくわからないんだけど、Clone or downloadのDownload ZIPでダウンロードできる模様。
展開すると、Distributionのフォルダにsqlite3.dllとSQLite3_StdCall.dllが入っている。sqlite3.dllは、SQLiteのエンジンが入ったDLL。SQLite3_StdCall.dllは、sqliteのAPIをVBAからアクセスできるようにしたラップ関数が入ったDLLぽい。
Distributionのフォルダには、サンプルらしきExcelファイルがある。
開いてみよう。
SQLiteForExcel_64.xlsmを開いてみる
.png)
シートにはなにも書いてない。
Visual Basic Editorを起動してみる。
.png)
なんかあるぞ。
標準モジュールに、Sqlite3とSqliteDemoのふたつが存在している。
Sqlite3の方には、SQLITE_OKとかSQLiteのAPIでおなじみの定数定義があったりする。
おー、間違いなくSQLite用みたいだ。
Sqlite3Demoの方は、デモ用か。AllTestsでテストできるのか。
イミディエイトを開いておいて、マクロの実行からAllTestsを実行してみる。
.png)
なんかテストした!
本日は、ここまで。
「改訂第4版SQLポケットリファレンス」は、SQLiteにも対応しています。
SQLを勉強したいという方には以下の本をオススメしたい。

SQLiteのサイト
「SQLite ODBC」 Excel AccessからSQLiteデータベースを使用する
SQLiteでのデータ型
SQLite Androidアプリ開発 SQLiteデータベースを使用する
SQLポケットリファレンス 台湾版SQLポケットリファレンス 台湾版の紹介
SQLポケリが第4版になりました
サイト内を検索
Webアプリ全盛な時代なのに、現場ではExcel使ってデータ入力したり、帳票出力するっていうところがいまだに多いようである。特に、街の小さな工場とか、商店とか。
Oracleデータベース使って、Webサーバと連携して、JavaScriptでリッチなクライアントを作成して、というのが流行りではあるものの「それはIT業界に限った話」でしかないのかも。
そもそも、小さな工場ならデータベースを使ったシステムなんか要らないのかも。
しかし、どういうわけか「現場の人はExcel好き」だったりする。ExcelのVLOOKUPやMATCH+INDEXじゃあパフォーマンス的に限界があるから、データベースに移行してくださいよ。といってもなかなか受け入れてもらえなかったりする。
普通にシステムを作成していても、Excelシートでデータを見たいんだけど...っていう要望が多かったり...
なぜか?
VBAが苦手。ましてやSQLなんて意味不明。Excel関数でできるじゃん。
という人が多いのであろう。
Excel使っているのなら、Access入れれば結構いい感じのシステムになりそうなのに。なんでイマドキMATCHやらINDEXとかのExcel関数使うのよ。もう。
Officeのプロフェッショナルは高い
Accessは、別に買わないといけない。
Excel、Word、OutlookはOfficeのセットなのだが、ここにAccessが入っていないので、高い方のOfficeを買わないといけない。それがネックなのか...

Microsoft Access 2016 (最新)|オンラインコード版
- 出版社/メーカー: マイクロソフト
- メディア: Software Download
MS Accessの記事についてはこちらを参照されたし
じゃあ、SQL Server Express入れてしまえばいいじゃん。と思うのだが、これはシステム屋が考えることらしい。無料で使えるといっても、データベースサーバを導入することについては「敷居が高い」と思われている。
うーん。まぁねぇ。専用のサーバマシンを導入したくなるし、運用面を考えるとなぁ...
MySQLやPostgreSQLという線もあるのではあるが、こっちは一層敷居が高くなってしまう。
データベースサーバを入れたら、複数のユーザで使えるようなシステムにできるので、かなり効率アップできると思うのだが...
ちょっと話を整理する
Accessを買うのがもったいない
別にデータベースサーバが欲しいわけじゃない
ちょっと遅いけどExcelで十分じゃない
ということなのかも知れない。
じゃあ、Excel+SQLiteで万事うまくいくのでは?
そう思っている人も多いらしく「SQLite for Excel」というパッケージが存在する。
ExcelからSQLiteを使うときは、SQLiteのODBCドライバを入れる方法もある。
SQLite ODBCの記事
今回は、SQLite for Excelをやってみたい。
SQLite for Excelは以下のURLからダウンロードできる
SQLite for Excel
GitHubってよくわからないんだけど、Clone or downloadのDownload ZIPでダウンロードできる模様。
展開すると、Distributionのフォルダにsqlite3.dllとSQLite3_StdCall.dllが入っている。sqlite3.dllは、SQLiteのエンジンが入ったDLL。SQLite3_StdCall.dllは、sqliteのAPIをVBAからアクセスできるようにしたラップ関数が入ったDLLぽい。
Distributionのフォルダには、サンプルらしきExcelファイルがある。
開いてみよう。
SQLiteForExcel_64.xlsmを開いてみる
.png)
シートにはなにも書いてない。
Visual Basic Editorを起動してみる。
.png)
なんかあるぞ。
標準モジュールに、Sqlite3とSqliteDemoのふたつが存在している。
Sqlite3の方には、SQLITE_OKとかSQLiteのAPIでおなじみの定数定義があったりする。
おー、間違いなくSQLite用みたいだ。
Sqlite3Demoの方は、デモ用か。AllTestsでテストできるのか。
イミディエイトを開いておいて、マクロの実行からAllTestsを実行してみる。
.png)
なんかテストした!
本日は、ここまで。
「改訂第4版SQLポケットリファレンス」は、SQLiteにも対応しています。
SQLを勉強したいという方には以下の本をオススメしたい。

Access クエリ 徹底活用ガイド ~仕事の現場で即使える
- 作者: 朝井 淳
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2018/05/25
- メディア: 大型本
SQLiteのサイト
関連記事
「SQLite ODBC」 Excel AccessからSQLiteデータベースを使用する
SQLiteでのデータ型
SQLite Androidアプリ開発 SQLiteデータベースを使用する
SQLポケットリファレンス 台湾版SQLポケットリファレンス 台湾版の紹介
SQLポケリが第4版になりました
サイト内を検索
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版 [SQLポケリ]
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
みなさん、こんにちは。本日もSQLポケットリファレンスの話題である。
前にも紹介したと思うが、最近では書籍の電子化が当たり前になってきている。SQLポケットリファレンスも改訂第3版を電子化するかどうか、といった話があったが、見送られていた。当時は、電子出版したら不正コピーが横行するのではないか、という心配があったからである。
そんな心配もあったが、時代の流れは電子化される方向に動いている。今回の改訂で、電子化されることになったのである。以下のURLから購入することができる。
[改訂第4版]SQLポケットリファレンス
https://gihyo.jp/dp/ebook/2016/978-4-7741-8826-3
技術評論社では、電子版と紙の本とで価格に差がない。どちらも同じ1980円。
電子版だと、印税率が高い。なので、私としては、電子版を購入してもらった方が嬉しいのであるが、電子版の売れ行きはあまり「よろしくない」らしい。
電子版は、PCやタブレットで閲覧することになる(PDFでダウンロードできる)。リファレンス的な内容の本は「ネット検索した方が早い」という場合が多いので、わざわざ、電子版の書籍を購入しなくても...
ということみたいである。
PDFを開いて検索するっていう方法もあるのだけれど...
電子機器持ち込み禁止
システム開発の現場によっては、「電子機器持ち込み禁止」というところがあるらしい。個人情報の流出が問題になるような、データセンターに入って開発や保守作業するのであれば、当然かも知れない。
PCはもちろんのこと、携帯電話、タブレット、デジカメ、USBメモリなどなど、今やちょっとしたデジタル機器でも数ギガのデータを入れることができるので、簡単に大量のデータを持ち出すことができてしまう。
そんな時は、紙媒体の資料を持ち込んで作業する、ということをするらしい(聞いた話なので)。
ふーん、なるほどね。それならSQLポケットリファレンスは「もってこい」じゃないですか。
でも、「電子機器持ち込み禁止」な現場で働いている開発者って、そう何人も居ないよね。あまり、期待はできないが、そんな辛い立場で開発している方は、紙媒体の「改訂第4版SQLポケットリファレンス」を宜しくお願いします。
マルチディスプレイ
普段システム開発している時は、Visual StudioやEclipseなんかのIDEを立ち上げてますよね。多分、ディスプレイを占有しているはず。
SQLの文法が分からないぞ、というときにSQLポケリを取り出して見ていると思う。電子版なら、PDFを開いてディスプレイ上で閲覧できる。サブディスプレイに出しておけば、とっても便利じゃない?サブディスプレイがない?それなら、スマホやタブレットに入れて見たらどう。
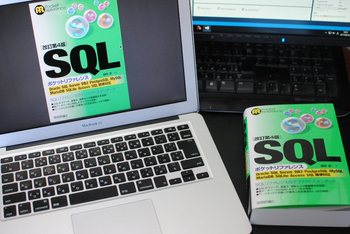
どちらでもお好きな方をどうぞ。
関連記事
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
サイト内を検索
みなさん、こんにちは。本日もSQLポケットリファレンスの話題である。
前にも紹介したと思うが、最近では書籍の電子化が当たり前になってきている。SQLポケットリファレンスも改訂第3版を電子化するかどうか、といった話があったが、見送られていた。当時は、電子出版したら不正コピーが横行するのではないか、という心配があったからである。
そんな心配もあったが、時代の流れは電子化される方向に動いている。今回の改訂で、電子化されることになったのである。以下のURLから購入することができる。
[改訂第4版]SQLポケットリファレンス
https://gihyo.jp/dp/ebook/2016/978-4-7741-8826-3
技術評論社では、電子版と紙の本とで価格に差がない。どちらも同じ1980円。
電子版だと、印税率が高い。なので、私としては、電子版を購入してもらった方が嬉しいのであるが、電子版の売れ行きはあまり「よろしくない」らしい。
電子版は、PCやタブレットで閲覧することになる(PDFでダウンロードできる)。リファレンス的な内容の本は「ネット検索した方が早い」という場合が多いので、わざわざ、電子版の書籍を購入しなくても...
ということみたいである。
PDFを開いて検索するっていう方法もあるのだけれど...
電子機器持ち込み禁止
システム開発の現場によっては、「電子機器持ち込み禁止」というところがあるらしい。個人情報の流出が問題になるような、データセンターに入って開発や保守作業するのであれば、当然かも知れない。
PCはもちろんのこと、携帯電話、タブレット、デジカメ、USBメモリなどなど、今やちょっとしたデジタル機器でも数ギガのデータを入れることができるので、簡単に大量のデータを持ち出すことができてしまう。
そんな時は、紙媒体の資料を持ち込んで作業する、ということをするらしい(聞いた話なので)。
ふーん、なるほどね。それならSQLポケットリファレンスは「もってこい」じゃないですか。
でも、「電子機器持ち込み禁止」な現場で働いている開発者って、そう何人も居ないよね。あまり、期待はできないが、そんな辛い立場で開発している方は、紙媒体の「改訂第4版SQLポケットリファレンス」を宜しくお願いします。
マルチディスプレイ
普段システム開発している時は、Visual StudioやEclipseなんかのIDEを立ち上げてますよね。多分、ディスプレイを占有しているはず。
SQLの文法が分からないぞ、というときにSQLポケリを取り出して見ていると思う。電子版なら、PDFを開いてディスプレイ上で閲覧できる。サブディスプレイに出しておけば、とっても便利じゃない?サブディスプレイがない?それなら、スマホやタブレットに入れて見たらどう。
どちらでもお好きな方をどうぞ。
関連記事
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
サイト内を検索
みなさんこんにちは、本日は、重大発表があります。SQLポケットリファレンス第4版 [SQLポケリ]
なんと、SQLポケットリファレンスが第4版になりました。
じゃーん。

例によって、歴代のSQLポケットリファレンスを並べてみると。

なかなか壮観である。
えーと、なんか自慢みたいでいやなのだが、増刷になると1冊だけだが、本を出版社からもらえる。増刷する際に、誤記を訂正できるので、その確認のためにくれるのだが、SQLポケットリファレンスの場合、けっこう増刷しているので、何冊もある。
机の上にあってもじゃまなので、古い版のやつは、押し入れにしまってあったりする。
刷数が違うやつも並べてみたら、机の上に乗りきらなかった。うーん、歴史を感じるなぁ。最初が1999年(平成11年)だから、もう17年か。
初版 1999年
第2版 2003年
第3版 2009年
第4版 2017年
今回の改訂では、対応データベースがひとつ増えた。SQLiteが増えている。日々、AndroidやiOSなどの携帯端末上でアプリを開発している、という開発者も多いことであろう。そんな、方々にもSQLポケットリファレンスを使ってもらおう。というのが今回の改訂の目論見のひとつでもあった。
組み込み系では、SQLなんて使わなくても、配列で十分、とか... サイズ的に重たいんじゃない?といった意見も多い。というか、「多かった」かなぁ。しかし、AndroidやiPhoneには標準で入っているし。これを使わない手はない。
それに、今や組み込みにしても、ギガ単位でストレージを持つことも珍しくない。流石にOracleをフルセットで導入、とかは無理かも知れないが、SQLiteなら数百キロくらいでOK。raspberry piなんか、メモリ1ギガも積んでるし。5000円なのに。
そういえば、昔Oracle Liteっていうのがあったなぁ。
ということで、進化を続けるSQLポケットリファレンスなのであるが、改訂する度にページ数は増えている。当然、内容を充実させてきた結果ではあるが。ちょっとまとめてみよう。
そんな感じで進化を続けてきたSQLポケットリファレンスであるが、変わっていないことがひとつある。
お気づきであろうか。
カバーの色が「緑」っていうことも、変化していないうちのひとつではあるが、それより決定的に変化していないものがある。
それは、
なんと、お値段がそのまま1980円なのである。
ページ数が増えればそれだけ、本の値段は高くなるのが普通。印刷するのにコストがかかるから。しかしながら、お値段は変わらず1980円なのである。
消費税が5%から8%になり、税込みでいうと、2079円から2138円に値上げされてしまった感があるが、本体価格は発売以来ずーと1980円なのである。
気になって、他のポケットリファレンスシリーズの価格も調べてみると、2000円台のものが多い。最近発行されたものは、2500円くらい。他の出版社さんでも2000円くらいが多いか。
いいんですかねぇ、こんなにお安くて。
まぁ、戦略としてはよいと思う。内容が充実しているのに、1980円なら「安い」と思えるでしょう。Web関係の開発者が、JavaScriptリファレンスが必要という状況で、SQLもあった方がよいか... ということになり、1980円なら、ついでに購入。っていうことが期待できそう。
なんにしても、新しくなった「改訂第4版SQLポケットリファレンス」をどうぞよろしくお願い致します。
サイト内を検索
じゃーん。
例によって、歴代のSQLポケットリファレンスを並べてみると。
なかなか壮観である。
えーと、なんか自慢みたいでいやなのだが、増刷になると1冊だけだが、本を出版社からもらえる。増刷する際に、誤記を訂正できるので、その確認のためにくれるのだが、SQLポケットリファレンスの場合、けっこう増刷しているので、何冊もある。
机の上にあってもじゃまなので、古い版のやつは、押し入れにしまってあったりする。
刷数が違うやつも並べてみたら、机の上に乗りきらなかった。うーん、歴史を感じるなぁ。最初が1999年(平成11年)だから、もう17年か。
初版 1999年
第2版 2003年
第3版 2009年
第4版 2017年
今回の改訂では、対応データベースがひとつ増えた。SQLiteが増えている。日々、AndroidやiOSなどの携帯端末上でアプリを開発している、という開発者も多いことであろう。そんな、方々にもSQLポケットリファレンスを使ってもらおう。というのが今回の改訂の目論見のひとつでもあった。
組み込み系では、SQLなんて使わなくても、配列で十分、とか... サイズ的に重たいんじゃない?といった意見も多い。というか、「多かった」かなぁ。しかし、AndroidやiPhoneには標準で入っているし。これを使わない手はない。
それに、今や組み込みにしても、ギガ単位でストレージを持つことも珍しくない。流石にOracleをフルセットで導入、とかは無理かも知れないが、SQLiteなら数百キロくらいでOK。raspberry piなんか、メモリ1ギガも積んでるし。5000円なのに。
そういえば、昔Oracle Liteっていうのがあったなぁ。
ということで、進化を続けるSQLポケットリファレンスなのであるが、改訂する度にページ数は増えている。当然、内容を充実させてきた結果ではあるが。ちょっとまとめてみよう。
| 版 | ページ数 | 対応DB |
| 初版 | 416 | Oracle、SQL Server、MS Access |
| 第2版 | 600 | Oracle、SQL Server、DB2、PostgreSQL、MySQL、MS Access |
| 第3版 | 640 | Oracle、SQL Server、DB2、PostgreSQL、MySQL、MS Access |
| 第4版 | 656 | Oracle、SQL Server、DB2、PostgreSQL、MySQL、SQLite、MS Access |
そんな感じで進化を続けてきたSQLポケットリファレンスであるが、変わっていないことがひとつある。
お気づきであろうか。
カバーの色が「緑」っていうことも、変化していないうちのひとつではあるが、それより決定的に変化していないものがある。
それは、
なんと、お値段がそのまま1980円なのである。
ページ数が増えればそれだけ、本の値段は高くなるのが普通。印刷するのにコストがかかるから。しかしながら、お値段は変わらず1980円なのである。
消費税が5%から8%になり、税込みでいうと、2079円から2138円に値上げされてしまった感があるが、本体価格は発売以来ずーと1980円なのである。
気になって、他のポケットリファレンスシリーズの価格も調べてみると、2000円台のものが多い。最近発行されたものは、2500円くらい。他の出版社さんでも2000円くらいが多いか。
いいんですかねぇ、こんなにお安くて。
まぁ、戦略としてはよいと思う。内容が充実しているのに、1980円なら「安い」と思えるでしょう。Web関係の開発者が、JavaScriptリファレンスが必要という状況で、SQLもあった方がよいか... ということになり、1980円なら、ついでに購入。っていうことが期待できそう。
なんにしても、新しくなった「改訂第4版SQLポケットリファレンス」をどうぞよろしくお願い致します。
関連記事
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
第4版には電子版もあります。
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
SQLポケットリファレンス 台湾版「最新SQL語法範例辭典」
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
第4版には電子版もあります。
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
SQLポケットリファレンス 台湾版「最新SQL語法範例辭典」
サイト内を検索
onclick事件 [SQLポケリ]
先日、ネタになりそうな話を聞いたので、久しぶりにブログを更新してみる。
ハンディターミナルを扱っている販売代理店の方と食事をする機会があり、その中で聞いた話である。
工場が中国にあるそうで、そことのやりとりも多いそうである。やりとりは英語が中心になるそうなのであるが、たまに日本語も入ってくるらしい。
とある日のメールに「onclick事件」がどうのこうのと書いてあったらしい。担当者は、何か工場で事件があったのか?とビビったようである。
何かのボタンをクリックしたら火を噴いたとか...
オチは、どうということはない。どうやら、eventのことは「事件」と訳されているというだけの話。
向こうの担当者は普通に、OnClickEventの話をしていたようなのだが、中途半端に訳してしまったものだから、混乱してしまったようである。しかし、
onclick事件
って書かれたらなんか意味深である。
気になって、「onclick事件」で検索してみたら、出てくる出てくる。これは結構笑える。
以前に、SQLポケットリファレンスの台湾版を紹介しているが、ここにも「何たら事件」がないかパラパラとめくってみた。

GUI系ではないので、イベントは出てこないか...
残念。
目次を見ていくと、面白いキーワードを発見。「物件資料表」て何だ。
物件、物件?、物件??、不動産関係の本じゃないんだけど、物件って何?
対応するページを見てみると、わかった。どうも「オブジェクト」が「物件」に訳されている。
ふーん。
「物件資料表」=「オブジェクトテーブル」
ということらしい。
サイト内を検索
ハンディターミナルを扱っている販売代理店の方と食事をする機会があり、その中で聞いた話である。
工場が中国にあるそうで、そことのやりとりも多いそうである。やりとりは英語が中心になるそうなのであるが、たまに日本語も入ってくるらしい。
とある日のメールに「onclick事件」がどうのこうのと書いてあったらしい。担当者は、何か工場で事件があったのか?とビビったようである。
何かのボタンをクリックしたら火を噴いたとか...
オチは、どうということはない。どうやら、eventのことは「事件」と訳されているというだけの話。
向こうの担当者は普通に、OnClickEventの話をしていたようなのだが、中途半端に訳してしまったものだから、混乱してしまったようである。しかし、
onclick事件
って書かれたらなんか意味深である。
気になって、「onclick事件」で検索してみたら、出てくる出てくる。これは結構笑える。
以前に、SQLポケットリファレンスの台湾版を紹介しているが、ここにも「何たら事件」がないかパラパラとめくってみた。
GUI系ではないので、イベントは出てこないか...
残念。
目次を見ていくと、面白いキーワードを発見。「物件資料表」て何だ。
物件、物件?、物件??、不動産関係の本じゃないんだけど、物件って何?
対応するページを見てみると、わかった。どうも「オブジェクト」が「物件」に訳されている。
ふーん。
「物件資料表」=「オブジェクトテーブル」
ということらしい。
関連記事
SQLポケットリファレンス 台湾版「SQL語法範例辭典」
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
SQLポケットリファレンス 台湾版「SQL語法範例辭典」
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
サイト内を検索
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る [SQLポケリ]
本日は、SQLネタである。
![DSC_1228[1].jpg](https://asai-atsushi.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f55/asai-atsushi/DSC_12285B15D.jpg)
少し前に、結合方法について書いてみた(INNER JOINとかの記事のことです)。
NATURAL JOINが最新の結合方法、と書いてみたりしたのだが、これよりもっと新しそうなのを発見してしまった。
「CROSS APPLY」というやつである。以前からその存在は知っていた(*1)のだが、Oracle12cで採用になったのでちょっと調べてみることにした。
こんな感じで使います。
*1
SQL Serverのマニュアルでxml列のメソッドnodes()を使うときに、CROSS APPLYを使っている。
CROSS APPLYはMS SQL Serverでは、2005からできることになっている。マニュアルには、テーブルを戻す関数をCROSS APPLYすると便利ですよ"的な"例が載っている。
そうなのか、じゃあやってみるか。
まずは、CROSS APPLYの左側に指定するテーブルを作成してみた。このテーブルfooに対してCROSS APPLYで交差適用(とでもいうのだろうか)、をやってみたいと思う。
CROSS APPLYの右側には、テーブル値を戻す関数を指定するといいよ、とのことなので、関数を作成してみる。引数でもらった値の行数分だけ連番を戻すような関数を作成する。
説明しなくてもいいよね。
この関数を実行したら、以下のような結果を戻す。
これで、CROSS APPLYの左右が揃った。fooとfun_barを結合してみるわけであるが、テーブルfooと関数func_barを単純に結合するのではなく、foo.aをfunc_barの引数に渡して結合したいのである。
そんな時に、CROSS APPLYを使うとよいらしい。違うかなぁ...まぁ、やってみよう。
func_barに渡した引数で戻りの行数が異なる。これを考慮して、交差結合した感じになった。
a=1の行 func_barの戻す行=1 (0)
a=2の行 func_barの戻す行=2 (0,1)
a=3の行 func_barの戻す行=3 (0,1,2)
まぁ、そういうもんでしょう。
CROSS APPLYの左右を逆にすることはできない。
はエラーになる。foo.aが最初に出現するので、これがわからん、と文句をいわれる。
マニュアルには関数なら便利だよ的なことが書いてあるので、関数じゃなければいけないかというと、そうでもない。テーブル値を戻せばよいだけなので、サブクエリでも良い。
もうひとつテーブルを作成してみよう。
barテーブルを作成した。これをSELECTするサブクエリをCROSS APPLYしてみよう。
できた。
a=3の行がなくなってしまっているが、「OUTER APPLY」にすれば取得可能となる。
えーと、これって普通のINNER JOINやLEFT JOINと「どう違うのだろう?」と思いません?
INNER JOINで書くとするのなら、以下のようにすればよいと思うのだが...
結合条件をサブクエリのWHEREで書いているか、FROMのONで書いているかの違いはあるのか。
CROSS APPLYを単にINNER JOINには変更できない。以下のようにすると、エラーになる。
ONで条件式を書いていない、というのは横に置いておくとしても、サブクエリの中で、fooを使うことはできない。fooはわかりません、というエラーになる。
ああ、そうか、こういう場合、SELECT句にサブクエリ書いて逃げてきたかも。でも、SELECT句に書くとスカラ値を返さなくてはいけなくなって、散々苦労した覚えが...
LATERALインラインビューというものがある。これを使えば、INNER JOINでもCROSS APPLYのようなことができてしまうのである。
LATERALインラインビューにするには、サブクエリの前にLATERALキーワードを付けるだけ。
SQL Serverでは、LATERALをサポートしていないので、エラーになってしまったが、Oracle12c、PostgreSQLでは実行できる。
OUTER APPLYにしたい場合は、LEFT JOINを使えば良い。
結合条件を冗長に記述しないといけないのが、ちょっと美しくないが、しょうがない。
ちなみに、LATERALはSQL標準である。CROSS APPLYばベンダ拡張。
SQLポケリ第4版にはCROSS APPLY載ってます。
2021/07/11追記
LATERALで冗長にONを書かないといけないと書いた。JOIN構文なのでONを記述しなければならないが、サブクエリと全く同じ条件を書く必要はないことがわかった。
なんなら、ON TRUEとしてしまうことも可能である。
と書くこともできる。
Postgresで確認。Oracleではできるか不明。
SQL NATURAL JOIN 自然結合 (というか結合のあれこれ)
SQL WITH句 再帰クエリー RECURSIVE SQLポケリ
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
ProxmoxにOracle23cを入れてみる【OL9には入らない】
データベースにおける正規表現【REGEXP】
サイト内を検索
![DSC_1228[1].jpg](https://asai-atsushi.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f55/asai-atsushi/DSC_12285B15D.jpg)
少し前に、結合方法について書いてみた(INNER JOINとかの記事のことです)。
NATURAL JOINが最新の結合方法、と書いてみたりしたのだが、これよりもっと新しそうなのを発見してしまった。
「CROSS APPLY」というやつである。以前からその存在は知っていた(*1)のだが、Oracle12cで採用になったのでちょっと調べてみることにした。
こんな感じで使います。
SELECT * FROM foo CROSS APPLY func_bar(foo.a) AS FB
*1
SQL Serverのマニュアルでxml列のメソッドnodes()を使うときに、CROSS APPLYを使っている。
CROSS APPLYはMS SQL Serverでは、2005からできることになっている。マニュアルには、テーブルを戻す関数をCROSS APPLYすると便利ですよ"的な"例が載っている。
そうなのか、じゃあやってみるか。
CREATE TABLE foo ( a INTEGER, b VARCHAR(10) ); INSERT INTO foo VALUES(1,'one'); INSERT INTO foo VALUES(2,'two'); INSERT INTO foo VALUES(3,'three');
まずは、CROSS APPLYの左側に指定するテーブルを作成してみた。このテーブルfooに対してCROSS APPLYで交差適用(とでもいうのだろうか)、をやってみたいと思う。
CROSS APPLYの右側には、テーブル値を戻す関数を指定するといいよ、とのことなので、関数を作成してみる。引数でもらった値の行数分だけ連番を戻すような関数を作成する。
CREATE FUNCTION func_bar(@no int)
RETURNS @result TABLE (a int)
AS
BEGIN
DECLARE @i int
SET @i = 0
WHILE @i < @no
BEGIN
INSERT INTO @result SELECT @i
SET @i = @i + 1
END
RETURN
END
説明しなくてもいいよね。
この関数を実行したら、以下のような結果を戻す。
SELECT * FROM func_bar(2); a ------ 0 1
これで、CROSS APPLYの左右が揃った。fooとfun_barを結合してみるわけであるが、テーブルfooと関数func_barを単純に結合するのではなく、foo.aをfunc_barの引数に渡して結合したいのである。
そんな時に、CROSS APPLYを使うとよいらしい。違うかなぁ...まぁ、やってみよう。
SELECT * FROM foo CROSS APPLY func_bar(foo.a) AS FB a b a_1 --------------- 1 one 0 2 two 0 2 two 1 3 three 0 3 three 1 3 three 2
func_barに渡した引数で戻りの行数が異なる。これを考慮して、交差結合した感じになった。
a=1の行 func_barの戻す行=1 (0)
a=2の行 func_barの戻す行=2 (0,1)
a=3の行 func_barの戻す行=3 (0,1,2)
まぁ、そういうもんでしょう。
CROSS APPLYの左右を逆にすることはできない。
SELECT * FROM func_bar(foo.a) AS FB CROSS APPLY foo
はエラーになる。foo.aが最初に出現するので、これがわからん、と文句をいわれる。
マニュアルには関数なら便利だよ的なことが書いてあるので、関数じゃなければいけないかというと、そうでもない。テーブル値を戻せばよいだけなので、サブクエリでも良い。
もうひとつテーブルを作成してみよう。
CREATE TABLE bar ( a INTEGER, b VARCHAR(20) ) INSERT INTO bar VALUES(1,'uno'); INSERT INTO bar VALUES(1,'一'); INSERT INTO bar VALUES(2,'due'); INSERT INTO bar VALUES(2,'二');
barテーブルを作成した。これをSELECTするサブクエリをCROSS APPLYしてみよう。
SELECT * FROM foo CROSS APPLY ( SELECT * FROM bar WHERE foo.a = bar.a ) AS SB a b a_1 a_2 -------------------- 1 one 1 uno 1 one 1 一 2 two 2 due 2 two 2 二
できた。
a=3の行がなくなってしまっているが、「OUTER APPLY」にすれば取得可能となる。
OUTER APPLY
SELECT * FROM foo OUTER APPLY ( SELECT * FROM bar WHERE foo.a = bar.a ) AS SB a b a_1 a_2 -------------------- 1 one 1 uno 1 one 1 一 2 two 2 due 2 two 2 二 3 three null null
えーと、これって普通のINNER JOINやLEFT JOINと「どう違うのだろう?」と思いません?
INNER JOINで書くとするのなら、以下のようにすればよいと思うのだが...
SELECT * FROM foo INNER JOIN ( SELECT * FROM bar ) AS SB ON foo.a = SB.a
結合条件をサブクエリのWHEREで書いているか、FROMのONで書いているかの違いはあるのか。
CROSS APPLYを単にINNER JOINには変更できない。以下のようにすると、エラーになる。
SELECT * FROM foo INNER JOIN ( SELECT * FROM bar WHERE foo.a = bar.a ) AS SB
ONで条件式を書いていない、というのは横に置いておくとしても、サブクエリの中で、fooを使うことはできない。fooはわかりません、というエラーになる。
ああ、そうか、こういう場合、SELECT句にサブクエリ書いて逃げてきたかも。でも、SELECT句に書くとスカラ値を返さなくてはいけなくなって、散々苦労した覚えが...
LATERAL
LATERALインラインビューというものがある。これを使えば、INNER JOINでもCROSS APPLYのようなことができてしまうのである。
LATERALインラインビューにするには、サブクエリの前にLATERALキーワードを付けるだけ。
SELECT * FROM foo INNER JOIN LATERAL ( SELECT * FROM bar WHERE foo.a = bar.a ) SB
SQL Serverでは、LATERALをサポートしていないので、エラーになってしまったが、Oracle12c、PostgreSQLでは実行できる。
OUTER APPLYにしたい場合は、LEFT JOINを使えば良い。
SELECT * FROM foo LEFT JOIN LATERAL ( SELECT * FROM bar WHERE foo.a = bar.a ) SB ON foo.a = SB.a
結合条件を冗長に記述しないといけないのが、ちょっと美しくないが、しょうがない。
ちなみに、LATERALはSQL標準である。CROSS APPLYばベンダ拡張。
SQLポケリ第4版にはCROSS APPLY載ってます。
2021/07/11追記
LATERALで冗長にONを書かないといけないと書いた。JOIN構文なのでONを記述しなければならないが、サブクエリと全く同じ条件を書く必要はないことがわかった。
なんなら、ON TRUEとしてしまうことも可能である。
SELECT * FROM foo LEFT JOIN LATERAL ( SELECT * FROM bar WHERE foo.a = bar.a ) SB ON TRUE
と書くこともできる。
Postgresで確認。Oracleではできるか不明。
関連記事
SQL NATURAL JOIN 自然結合 (というか結合のあれこれ)
SQL WITH句 再帰クエリー RECURSIVE SQLポケリ
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
ProxmoxにOracle23cを入れてみる【OL9には入らない】
データベースにおける正規表現【REGEXP】
サイト内を検索
テーブルのパーティッション分割 [SQLポケリ]
本日のネタもデータベースである。
最近のデータベースでは、テーブルを「パーティッションに区切る」ということが可能。
最近といっても、もうかなり前からかも。えーと、Oracleだと、10gくらいからか?
しかし、Enterprise Editionじゃないと使えないっぽい。ケチだよね、Oracleって。
DB2はV9から。なんだ、やっぱり割と最近じゃない?
SQL Serverは、2005。ということは、約10年前。10年ひと昔、というから割と古いのかも。
MySQLでは、5.1からか。PostgreSQLは一応は対応しているのか。
でもってパーティッションに分割すると、どんないいことがあるかというと。
・パフォーマンスアップ
・データの管理がしやすくなる
といったところか。
テーブルをパーティッションに区切ると効率的なのは、ログデータのように、履歴を保存しておくような場合。
パーティッションに分割するといっても、けっこういろいろなパターンがあるようなので、ここで一回整理しよう。
・レンジパーティッション
テーブルを時系列で分割するような分割方法。
2000年のデータ
2001年のデータ
2002年のデータ
のように、時間や数値の範囲で分割していく手法。
・リストパーティッション
テーブルのある列をキーにして分割するような分割方法。
男性のデータ
女性のデータ
のように、データの取る値によって、保存先のパーティッションを決定する方法。
・ハッシュパーティッション
テーブルのある列から、ハッシュ値を計算して、その値から分割する方法。
分割したいのだけど、どの値で分割してよいかわからない場合に、ハッシュパーティッションが有効。
・コンポジットパーティッション
なんかよくわからないが、リストとハッシュの組み合わせ、とかでやるものか。
まぁ、メジャーなのは、以下の3つか。
・レンジパーティッション
・リストパーティッション
・ハッシュパーティッション
ひとつひとつみていこうか。
レンジパーティッション
これは、紹介した通り、値の範囲で分割しましょう、という考えやすい分割方法である。
パーティッションの定義は、CREATE TABLEでテーブルを作成する際にする。後で変更する場合は、ALTER TABLEを使う。
上記のようなテーブルがあったとする。普通に実行すれば、テーブルが作成されるが、パーティッション分割は行われない。
これをパーティッションに分割してみよう。
パーティッションに分割するためには、PARTITION句が必要になる。PARTITION句では、どの列で分割を行うのか、それに加え、どのような条件で分割を行うのかを指定する。
partition_testでは、日付のd列を使って、レンジパーティッションで分割するようにしたいと思う。レンジパーティッションでは、PARTITION BY RANGEを使用する。ここまでをSQLにしてみると、以下のようになる。
まだ十分でないため、実行してもエラーになる。
PARTITION BYには、分割のための条件式が必要になる。分割したい数分だけパーティッションの名前と条件を列挙する。
partition_testでは、年を単位にしてパーティッションを分割しようと思う。
これで、ふたつのパーティッションに分割されることになる。必要なら、TABLESPACEを指定して、保存先のストレージを分けるということもできる。
日付で分割する場合、パーティッションのメンテナンスが必要になる。つまり2017年になったら、パーティッションを増やしてやる必要がある。保存しておく必要がなくなった古いデータをパーティッションごと削除する、ということも可能である。既存テーブルへのパーティッションの追加、削除は、ALTER TABLE命令で行う。
パーティッションの追加
パーティッションの削除
パーティッション内のレコードは全部なくなってしまうので注意。
この他、パーティッションのメンテナンスとしては、既存のパーティッションをさらに分割(SPLIT)したり、ふたつのパーティッションを統合(MERGE)したりすることができる。
パーティッションを作成したからといって、INSERTやUPDATEを行う際に、パーティッションを意識する必要はない。普通にINSERTすればよい。
2016-01-01より前のレコードは、パーティッション year1 に、2017-01-01より前のレコードは、パーティッション year2 に自動的に記録される。
しかしである。記録すべきパーティッションが見つからない場合は、エラーになるので注意したい。こういった場合、最大値までのパーティッションを作成しておくと、間違いがない。最大値は、MAXVALUEで指定可能。
SELECTで問い合わせを行う際には、パーティションを意識した方が、パフォーマンス向上が期待できる(かも知れない)。
データの検索を2015年のデータに限って行いたいのであれば、パーティッションyear1のみからデータを検索すれば、高速。パーティッションを指定するには、以下のようにする。
だいたい、こんな感じだろうか。
では、次に、リストパーティッションについてみていこう。
リストパーティッション
レンジパーティッションは、値の範囲でパーティッション分割を行っている。リストパーティッションでは、キーとなる列の値をリストで定義する。
ユーザ管理が行われているテーブルを例にしてみる。以下のように、レコードデータにユーザIDが付けられている。多くのWebアプリケーションシステムでユーザ管理が行われていると思う。今回は、そういったシステムでユーザIDをキーにして、パーティッション分割を行ってみる想定である。
まずは、テーブルの定義を見てみよう。
userId列が、ユーザIDを示す列である。通常、ユーザ間のデータ共有ってまず行われない。ユーザ間のコミュニケーションが目的のシステムであれば話は別であるが、ブログとか、ショッピングサイトなら、他ユーザの情報は見えないし、見せてはいけないものとなる。
ユーザごとに、パーティッション分割してしまえば、何かと便利なんじゃないか、という発想である。
こういった用途で、リストパーティッションを使うことができる。リストパーティッションは、PARTITION BY LISTで定義する。partition_test2では、userIdをキーに分割したいので、PARTITION BY LIST (userId)とする。レンジパーティッション同様に、分割するパーティッションを列挙していくが、分割の条件がLESS THANではなく、単にVALUESに値を列挙するだけとなる。
じゃーん。こんな感じでパーティッション分割してみた。
ユーザuser1とuser2は同じパーティッションlist1に含まれることになる。user3は単独でパーティッションlist2に記録される。その他のユーザは、listxに入ることになる。
データの追加は通常のINSERTでOK。
パーティッションを指定することも可能ではあるが、あまりメリットはない。
間違えたパーティッションにINSERTしようとするとエラーになる。
レコードを検索する際に、パーティッション指定をすると、便利かも知れない。
パーティッション分割していないテーブルだとWHERE条件でユーザIDを指定しないといけない。
上記の例では、user1とuser2が同じパーティッションに入るので、やはりWHERE条件は必要になるかも知れないが、ユーザひとりについてひとつのパーティッションを割り当てます、というルールにすれば、そのテーブルをそのユーザ専用にすることができる。うまいことキーを設定してやれば、めんどうな結合条件を省略できるのでは、という話である。
これ開発中のシステムでも使いたいな、でもEnterprise Editionじゃないとだめなのか。
ハッシュパーティッション
レンジ、リストとふたつのパーティッションをみてきた。どちらもパーティッションに分割するためのキーが必要であったが、キーに対してひとつの列しか与えることができない。PARTITION BY RANGE (a,b,c) ということはできないのである。PARTITION BY LISTでも同様。
複数の列からパーティッション分割の条件を設定したい場合は、ハッシュパーティッションを使用すればよい。
前の例では、ユーザIDでリストパーティッション分割を行った。大規模なシステムでは、ユーザーIDだけではなく、ドメインとユーザIDでユーザ管理できることが往々にしてある。その場合、以下のようなテーブルになるであろう。
domainとuserIdでユニークになるようなデータ構造となる。パーティッション分割する際に、domainだけでは不十分。userIdも付けたい。しかし、複数列を許してくれない。ハッシュパーティッションにすれば、この問題を解決できる。
ハッシュパーティッションでは、複数の値からひとつの「ハッシュ値」を計算し、それを元にパーティッション分割する。この値のときは、このパーティッションに記録する、という条件を指定することはできない。データベースシステムの方で勝手に記録先が決定してしまう。
ハッシュ値の特性から、同じ値を与えれば、同じ記録先になる。例えば、キー'domain1','user1'のレコードがパーティッションhash1に記録されたとする。以降、パーティッション分割数を変更しない限り、キー'domain1','user1'の記録先は、常にパーティッションhash1に記録される。
どのパーティッションに記録されたかを調べるには、USER_OBJECTSテーブルの、SUBOBJECT_NAMEを参照するとわかる。
USER_OBJECTSテーブルのOBJECT_IDを調べるには、DBMS_ROWID.ROWID_OBJECT(rowid)を使用する。rowidは、レコードの疑似列。
よくわからないでしょうから、SELECT命令にします。
今回はここまでとする。
サイト内を検索
最近のデータベースでは、テーブルを「パーティッションに区切る」ということが可能。
最近といっても、もうかなり前からかも。えーと、Oracleだと、10gくらいからか?
しかし、Enterprise Editionじゃないと使えないっぽい。ケチだよね、Oracleって。
DB2はV9から。なんだ、やっぱり割と最近じゃない?
SQL Serverは、2005。ということは、約10年前。10年ひと昔、というから割と古いのかも。
MySQLでは、5.1からか。PostgreSQLは一応は対応しているのか。
でもってパーティッションに分割すると、どんないいことがあるかというと。
・パフォーマンスアップ
・データの管理がしやすくなる
といったところか。
テーブルをパーティッションに区切ると効率的なのは、ログデータのように、履歴を保存しておくような場合。
パーティッションに分割するといっても、けっこういろいろなパターンがあるようなので、ここで一回整理しよう。
・レンジパーティッション
テーブルを時系列で分割するような分割方法。
2000年のデータ
2001年のデータ
2002年のデータ
のように、時間や数値の範囲で分割していく手法。
・リストパーティッション
テーブルのある列をキーにして分割するような分割方法。
男性のデータ
女性のデータ
のように、データの取る値によって、保存先のパーティッションを決定する方法。
・ハッシュパーティッション
テーブルのある列から、ハッシュ値を計算して、その値から分割する方法。
分割したいのだけど、どの値で分割してよいかわからない場合に、ハッシュパーティッションが有効。
・コンポジットパーティッション
なんかよくわからないが、リストとハッシュの組み合わせ、とかでやるものか。
まぁ、メジャーなのは、以下の3つか。
・レンジパーティッション
・リストパーティッション
・ハッシュパーティッション
ひとつひとつみていこうか。
レンジパーティッション
これは、紹介した通り、値の範囲で分割しましょう、という考えやすい分割方法である。
パーティッションの定義は、CREATE TABLEでテーブルを作成する際にする。後で変更する場合は、ALTER TABLEを使う。
CREATE TABLE partition_test ( no INTEGER, d DATE, amount INTEGER )
上記のようなテーブルがあったとする。普通に実行すれば、テーブルが作成されるが、パーティッション分割は行われない。
これをパーティッションに分割してみよう。
パーティッションに分割するためには、PARTITION句が必要になる。PARTITION句では、どの列で分割を行うのか、それに加え、どのような条件で分割を行うのかを指定する。
partition_testでは、日付のd列を使って、レンジパーティッションで分割するようにしたいと思う。レンジパーティッションでは、PARTITION BY RANGEを使用する。ここまでをSQLにしてみると、以下のようになる。
CREATE TABLE partition_test ( no INTEGER, d DATE, amount INTEGER ) PARTITION BY RANGE (d)
まだ十分でないため、実行してもエラーになる。
PARTITION BYには、分割のための条件式が必要になる。分割したい数分だけパーティッションの名前と条件を列挙する。
partition_testでは、年を単位にしてパーティッションを分割しようと思う。
CREATE TABLE partition_test (
no INTEGER,
d DATE,
amount INTEGER
)
PARTITION BY RANGE (d) (
PARTITION year1 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2016-01-01', 'YYYY-MM-DD')),
PARTITION year2 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2017-01-01', 'YYYY-MM-DD'))
)
これで、ふたつのパーティッションに分割されることになる。必要なら、TABLESPACEを指定して、保存先のストレージを分けるということもできる。
日付で分割する場合、パーティッションのメンテナンスが必要になる。つまり2017年になったら、パーティッションを増やしてやる必要がある。保存しておく必要がなくなった古いデータをパーティッションごと削除する、ということも可能である。既存テーブルへのパーティッションの追加、削除は、ALTER TABLE命令で行う。
パーティッションの追加
ALTER TABLE partition_test
ADD PARTITION year3 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2018-01-01', 'YYYY-MM-DD'))
パーティッションの削除
ALTER TABLE partition_test DROP PARTITION year1
パーティッション内のレコードは全部なくなってしまうので注意。
この他、パーティッションのメンテナンスとしては、既存のパーティッションをさらに分割(SPLIT)したり、ふたつのパーティッションを統合(MERGE)したりすることができる。
パーティッションを作成したからといって、INSERTやUPDATEを行う際に、パーティッションを意識する必要はない。普通にINSERTすればよい。
INSERT INTO partition_test VALUES(1, '2015-01-01', 10); INSERT INTO partition_test VALUES(2, '2015-12-31', 20); INSERT INTO partition_test VALUES(3, '2016-01-01', 30); INSERT INTO partition_test VALUES(4, '2016-12-31', 40);
2016-01-01より前のレコードは、パーティッション year1 に、2017-01-01より前のレコードは、パーティッション year2 に自動的に記録される。
しかしである。記録すべきパーティッションが見つからない場合は、エラーになるので注意したい。こういった場合、最大値までのパーティッションを作成しておくと、間違いがない。最大値は、MAXVALUEで指定可能。
CREATE TABLE partition_test (
no INTEGER,
d DATE,
amount INTEGER
)
PARTITION BY RANGE (d) (
PARTITION year1 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2016-01-01', 'YYYY-MM-DD')),
PARTITION year2 VALUES LESS THAN(TO_DATE('2017-01-01', 'YYYY-MM-DD')),
PARTITION yearx VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
SELECTで問い合わせを行う際には、パーティションを意識した方が、パフォーマンス向上が期待できる(かも知れない)。
データの検索を2015年のデータに限って行いたいのであれば、パーティッションyear1のみからデータを検索すれば、高速。パーティッションを指定するには、以下のようにする。
SELECT * FROM partition_test PARTITION(year1)
だいたい、こんな感じだろうか。
では、次に、リストパーティッションについてみていこう。
リストパーティッション
レンジパーティッションは、値の範囲でパーティッション分割を行っている。リストパーティッションでは、キーとなる列の値をリストで定義する。
ユーザ管理が行われているテーブルを例にしてみる。以下のように、レコードデータにユーザIDが付けられている。多くのWebアプリケーションシステムでユーザ管理が行われていると思う。今回は、そういったシステムでユーザIDをキーにして、パーティッション分割を行ってみる想定である。
まずは、テーブルの定義を見てみよう。
CREATE TABLE partition_test2 ( userId VARCHAR2(10) NOT NULL, no INTEGER NOT NULL, d DATE, amount INTEGER, PRIMARY KEY(userId, no) )
userId列が、ユーザIDを示す列である。通常、ユーザ間のデータ共有ってまず行われない。ユーザ間のコミュニケーションが目的のシステムであれば話は別であるが、ブログとか、ショッピングサイトなら、他ユーザの情報は見えないし、見せてはいけないものとなる。
ユーザごとに、パーティッション分割してしまえば、何かと便利なんじゃないか、という発想である。
こういった用途で、リストパーティッションを使うことができる。リストパーティッションは、PARTITION BY LISTで定義する。partition_test2では、userIdをキーに分割したいので、PARTITION BY LIST (userId)とする。レンジパーティッション同様に、分割するパーティッションを列挙していくが、分割の条件がLESS THANではなく、単にVALUESに値を列挙するだけとなる。
CREATE TABLE partition_test2 (
userId VARCHAR2(10) NOT NULL,
no INTEGER NOT NULL,
d DATE,
amount INTEGER,
PRIMARY KEY (userId, no)
)
PARTITION BY LIST (userId) (
PARTITION list1 VALUES ('user1', 'user2'),
PARTITION list2 VALUES ('user3'),
PARTITION listx VALUES (DEFAULT)
)
じゃーん。こんな感じでパーティッション分割してみた。
ユーザuser1とuser2は同じパーティッションlist1に含まれることになる。user3は単独でパーティッションlist2に記録される。その他のユーザは、listxに入ることになる。
データの追加は通常のINSERTでOK。
INSERT INTO partition_test2 VALUES('user1', 1, '2016-04-01', 100);
パーティッションを指定することも可能ではあるが、あまりメリットはない。
INSERT INTO partition_test2 PARTITION(list1) VALUES('user1', 2, '2016-04-02', 101);
間違えたパーティッションにINSERTしようとするとエラーになる。
INSERT INTO partition_test2 PARTITION(list2) VALUES('user1', 2, '2016-04-02', 101);
レコードを検索する際に、パーティッション指定をすると、便利かも知れない。
SELECT * FROM partition_test2 PARTITION(list1);
パーティッション分割していないテーブルだとWHERE条件でユーザIDを指定しないといけない。
SELECT * FROM partition_test2 WHERE userId = 'user1';
上記の例では、user1とuser2が同じパーティッションに入るので、やはりWHERE条件は必要になるかも知れないが、ユーザひとりについてひとつのパーティッションを割り当てます、というルールにすれば、そのテーブルをそのユーザ専用にすることができる。うまいことキーを設定してやれば、めんどうな結合条件を省略できるのでは、という話である。
これ開発中のシステムでも使いたいな、でもEnterprise Editionじゃないとだめなのか。
ハッシュパーティッション
レンジ、リストとふたつのパーティッションをみてきた。どちらもパーティッションに分割するためのキーが必要であったが、キーに対してひとつの列しか与えることができない。PARTITION BY RANGE (a,b,c) ということはできないのである。PARTITION BY LISTでも同様。
複数の列からパーティッション分割の条件を設定したい場合は、ハッシュパーティッションを使用すればよい。
前の例では、ユーザIDでリストパーティッション分割を行った。大規模なシステムでは、ユーザーIDだけではなく、ドメインとユーザIDでユーザ管理できることが往々にしてある。その場合、以下のようなテーブルになるであろう。
CREATE TABLE partition_test3 ( domain VARCHAR2(10) NOT NULL, userId VARCHAR2(10) NOT NULL, no INTEGER NOT NULL, d DATE, amount INTEGER, PRIMARY KEY (domain, userId, no) )
domainとuserIdでユニークになるようなデータ構造となる。パーティッション分割する際に、domainだけでは不十分。userIdも付けたい。しかし、複数列を許してくれない。ハッシュパーティッションにすれば、この問題を解決できる。
CREATE TABLE partition_test3 ( domain VARCHAR2(10) NOT NULL, userId VARCHAR2(10) NOT NULL, no INTEGER NOT NULL, d DATE, amount INTEGER, PRIMARY KEY (domain, userId, no) ) PARTITION BY HASH (domain, userId) ( PARTITION hash1, PARTITION hash2, PARTITION hash3 )
ハッシュパーティッションでは、複数の値からひとつの「ハッシュ値」を計算し、それを元にパーティッション分割する。この値のときは、このパーティッションに記録する、という条件を指定することはできない。データベースシステムの方で勝手に記録先が決定してしまう。
ハッシュ値の特性から、同じ値を与えれば、同じ記録先になる。例えば、キー'domain1','user1'のレコードがパーティッションhash1に記録されたとする。以降、パーティッション分割数を変更しない限り、キー'domain1','user1'の記録先は、常にパーティッションhash1に記録される。
どのパーティッションに記録されたかを調べるには、USER_OBJECTSテーブルの、SUBOBJECT_NAMEを参照するとわかる。
USER_OBJECTSテーブルのOBJECT_IDを調べるには、DBMS_ROWID.ROWID_OBJECT(rowid)を使用する。rowidは、レコードの疑似列。
よくわからないでしょうから、SELECT命令にします。
SELECT *
FROM (
SELECT DBMS_ROWID.ROWID_OBJECT(ROWID) object_id,
domain, userId
FROM partition_test3
)
NATURAL JOIN USER_OBJECTS
;
今回はここまでとする。
サイト内を検索
タグ:SQL
SQL NATURAL JOIN 自然結合 (というか結合のあれこれ) [SQLポケリ]
SQLの基本はテーブル。テーブル同士を結合するようなSELECT命令を作成して、帳票出力なり、画面表示なりを行っていくことが基本である。つまり結合は基本なわけであるが、その当たりの詳細は、「[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩」を是非読んでみて欲しい。
![[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus) [データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/510-kU4HwjL._SL160_.jpg)
さて、結合の方法には、歴史がある。RDBMSは、古くからある。最初のレガシーな結合は、というと以下のような感じで行っていた。何せ、SQLには歴史があるからねぇ。
FROM句には、テーブルを列挙するが、ここにはアクセスするテーブル名だけを書く。結合条件は書かない。
WHEREに行を選択する条件式を書くのだが、レガシーなSQLでは結合条件もここに書くのである。
結合の基本は「交差結合」。なので基本は、交差結合で得られる「直積」の中から「条件を付けて選び出す」というのが、結合の基本であるわけである。
一方、NATURAL JOINは次のように書くことができる
結合条件がテーブルの列から自動的に決定するので条件式を書かなくてよい。ここが便利なところである。
SQLのSELECT命令では結合を行うことが多いのだが、いろいろとやり方があり、歴史的に変化もしてきている。ちょっと結合のやり方を整理してみよう。
普通の結合は、普通の画面や帳票を作る上では、普通に便利であった。直積から、条件に一致する行だけを抽出する、といった単純な処理方法であるため、扱いやすかった。
しかし、である。
「例外」というのは、いつの世の世界でも存在するもので「データがまだ揃っていない状況でも画面表示したい」とか、バグで「データがない状態でもなんとか表示させたい」というあまり「美しくない理由」で"外部結合"という方法が編み出された(と思う。あくまで推測です)。
考え方自体はどれも同じであったが、実装方法が異なっていた。
例えば、Oracleでは、外部結合を以下のように行っていた。
「(+)」っていうなんか得体の知れない、独特の「演算子みたいなもの」を作ってしまったのである。
これに対して、MS SQL Serverでは、以下のように外部結合することができた。
演算子を追加することで、外部結合ができるようにしたのだが... Oracleとは違う。
そう、いわゆる方言なわけです。
この辺りのことは「[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩」にはあまり書いてない。SQLポケットリファレンスには書いてあるか。
どちらかというと、Oracleより、SQL Serverの方が素直な感じ、というか、自分の考えに近いので、受け入れ易いと思う。開発者としては、演算子が増えるのには、意外と抵抗がない。しかし、Oracleの外部結合のように、式のわけがわからない位置に、わけわからない、記号が来ると「パニック」になるわけです。(+)っていう演算子なんて「Oracle以外で見たことないし!」。
どちらが良いかは置いておいて、同じことをするのに、データベースごとにやり方が異なると、開発者は困るわけです。どっちにも対応できるように作っておけ、と言われてしまうと、#ifdefの山になってしまうわけで... これはソースを見ると「読み難い」んです。とっても。
でもって、標準化団体が動き出したわけです。
結合は、「JOIN」を使ってやりましょう。ということになったのである。JOINはFROM句に書く。結合には、交差結合、内部結合、外部結合などいろいろな種類がある。JOINでは、その前に種類を指定することができる。
CROSS JOIN なら、交差結合。
INNER JOIN なら、内部結合。
LEFT OUTER JOIN なら、左側のテーブルを残す外部結合。
RIGHT OUTER JOIN なら、右側。
FULL OUTER JOIN なら、両方残す。
と決めたわけです。
交差結合を除いて、結合条件を指定しなければならない。WHEREに書いてきたやつですね。JOINの左右にはテーブル名を書くのだが、その後に「ONを付けて、結合条件式を書く」と決定したのです。
という内部結合なら、以下のようにJOINで書くことができる。
外部結合でもやってみるか。
どちらもLEFT JOINを使って、
とすればOK。
OUTERは省略できる。
FULL OUTER JOINは、(+)や*=では、できない。
Oracleの(+)方式でやろうと思ったら、以下のようになる。
SQL Server方式なら以下
(+)の連続や、*=*演算子は使えないので、どちらもエラーになる。
FULL OUTER JOINはサポートしているデータベースなら実行できる。
どうでもいいが、syntax highlighterでOUTERとかJOINがハイライトされないが...
JOINくらいはあってもいいのではないかと...
後で見てみよう。
ついでに、CROSS JOINもやってみようか
CROSS JOINでは結合条件がない。
USING
時代が進むと、USINGを使った結合条件を書くことも可能になってきた。
普通にテーブルを作成したら、プライマリキーとなっている列は、列名に「気を配って」作成される。商品マスタの商品コード列は、syohin_cdという名前を付けておいて、別のテーブルで商品マスタを参照する場合は、syohin_cdという同じ名前の列を作成することでしょう。
なので、結合条件は、以下のような感じになることが多い。
結構、式が長いよね。
結合条件が同じ列名であるのなら、USINGを使うことができる。
おお、これなら書く量が少なくて済む。いいね。
USINGだと、括弧の中には、列名しか書けない。結合の両方のテーブルで「同じ列名であることが前提」となる。
同じ列名であっても、型が微妙に違っていたりすると問題が発生するかも知れない。
普通のテーブル設計では、データの紐付けに使用する列は、列名、型とも一致させておくことがセオリーであろう。USINGはそのようなスキーマになっていれば、問題なくUSINGを使うことができる。
USINGでは、条件式で使われる演算子は、=に限定される。BETWEENやら>を使うときは、ONにしないといけない。まぁ、普通の結合では、=しか使わないので、この点については問題ないかと。
外部結合でもUSINGが使えることもある(データベース依存?)。
SQL Server、DB2、AccessではUSINGは使えない。
長々と説明してきたが、今回紹介したかったのはNATURAL JOINである。NATURAL JOINは「一番新しい結合の方法」かもしれない。
すみません。NATURAL JOINがなかなか出てこないので、ブログのタイトルを少し変えました。
NATUAL JOINを使うと条件式を記述しなくてもよい。結合するテーブル同士で同じ名前の列をすべて等しい条件に自動的になる。
テーブルfooとbarが以下のようにスキーマ定義されていたとする。
NATURAL JOINすると結合条件は、暗黙的に「foo.a = bar.a」となる。
NATURAL JOINは、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLiteで使用できる。
本日は以上。
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る
第4版にはNATURAL JOIN載ってます
結合がわからないという初心者の方にはこちらがおススメです。
サイト内を検索
![[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus) [データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/510-kU4HwjL._SL160_.jpg)
[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)
- 作者: 朝井 淳
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2015/03/03
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
さて、結合の方法には、歴史がある。RDBMSは、古くからある。最初のレガシーな結合は、というと以下のような感じで行っていた。何せ、SQLには歴史があるからねぇ。
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a = bar.a
FROM句には、テーブルを列挙するが、ここにはアクセスするテーブル名だけを書く。結合条件は書かない。
WHEREに行を選択する条件式を書くのだが、レガシーなSQLでは結合条件もここに書くのである。
結合の基本は「交差結合」。なので基本は、交差結合で得られる「直積」の中から「条件を付けて選び出す」というのが、結合の基本であるわけである。
一方、NATURAL JOINは次のように書くことができる
SELECT * FROM foo NATURAL JOIN bar
結合条件がテーブルの列から自動的に決定するので条件式を書かなくてよい。ここが便利なところである。
SQLのSELECT命令では結合を行うことが多いのだが、いろいろとやり方があり、歴史的に変化もしてきている。ちょっと結合のやり方を整理してみよう。
外部結合
普通の結合は、普通の画面や帳票を作る上では、普通に便利であった。直積から、条件に一致する行だけを抽出する、といった単純な処理方法であるため、扱いやすかった。
しかし、である。
「例外」というのは、いつの世の世界でも存在するもので「データがまだ揃っていない状況でも画面表示したい」とか、バグで「データがない状態でもなんとか表示させたい」というあまり「美しくない理由」で"外部結合"という方法が編み出された(と思う。あくまで推測です)。
考え方自体はどれも同じであったが、実装方法が異なっていた。
例えば、Oracleでは、外部結合を以下のように行っていた。
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a = bar.a(+)
「(+)」っていうなんか得体の知れない、独特の「演算子みたいなもの」を作ってしまったのである。
これに対して、MS SQL Serverでは、以下のように外部結合することができた。
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a *= bar.a
演算子を追加することで、外部結合ができるようにしたのだが... Oracleとは違う。
そう、いわゆる方言なわけです。
この辺りのことは「[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩」にはあまり書いてない。SQLポケットリファレンスには書いてあるか。
どちらかというと、Oracleより、SQL Serverの方が素直な感じ、というか、自分の考えに近いので、受け入れ易いと思う。開発者としては、演算子が増えるのには、意外と抵抗がない。しかし、Oracleの外部結合のように、式のわけがわからない位置に、わけわからない、記号が来ると「パニック」になるわけです。(+)っていう演算子なんて「Oracle以外で見たことないし!」。
どちらが良いかは置いておいて、同じことをするのに、データベースごとにやり方が異なると、開発者は困るわけです。どっちにも対応できるように作っておけ、と言われてしまうと、#ifdefの山になってしまうわけで... これはソースを見ると「読み難い」んです。とっても。
でもって、標準化団体が動き出したわけです。
結合は、「JOIN」を使ってやりましょう。ということになったのである。JOINはFROM句に書く。結合には、交差結合、内部結合、外部結合などいろいろな種類がある。JOINでは、その前に種類を指定することができる。
CROSS JOIN なら、交差結合。
INNER JOIN なら、内部結合。
LEFT OUTER JOIN なら、左側のテーブルを残す外部結合。
RIGHT OUTER JOIN なら、右側。
FULL OUTER JOIN なら、両方残す。
と決めたわけです。
交差結合を除いて、結合条件を指定しなければならない。WHEREに書いてきたやつですね。JOINの左右にはテーブル名を書くのだが、その後に「ONを付けて、結合条件式を書く」と決定したのです。
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a = bar.a
という内部結合なら、以下のようにJOINで書くことができる。
SELECT * FROM foo INNER JOIN bar ON foo.a = bar.a
外部結合でもやってみるか。
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a = bar.a(+) SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a *= bar.a
どちらもLEFT JOINを使って、
SELECT * FROM foo LEFT JOIN bar ON foo.a = bar.a
とすればOK。
OUTERは省略できる。
FULL OUTER JOINは、(+)や*=では、できない。
Oracleの(+)方式でやろうと思ったら、以下のようになる。
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a(+) = bar.a(+)
SQL Server方式なら以下
SELECT * FROM foo, bar WHERE foo.a *=* bar.a
(+)の連続や、*=*演算子は使えないので、どちらもエラーになる。
FULL OUTER JOINはサポートしているデータベースなら実行できる。
SELECT * FROM foo FULL OUTER JOIN bar ON foo.a = bar.a
どうでもいいが、syntax highlighterでOUTERとかJOINがハイライトされないが...
JOINくらいはあってもいいのではないかと...
後で見てみよう。
ついでに、CROSS JOINもやってみようか
SELECT * FROM foo CROSS JOIN bar
CROSS JOINでは結合条件がない。
USING
時代が進むと、USINGを使った結合条件を書くことも可能になってきた。
普通にテーブルを作成したら、プライマリキーとなっている列は、列名に「気を配って」作成される。商品マスタの商品コード列は、syohin_cdという名前を付けておいて、別のテーブルで商品マスタを参照する場合は、syohin_cdという同じ名前の列を作成することでしょう。
なので、結合条件は、以下のような感じになることが多い。
syohin INNER JOIN uriage ON syohin.syohin_cd = uriage.syohin_cd
結構、式が長いよね。
結合条件が同じ列名であるのなら、USINGを使うことができる。
syohin INNER JOIN uriage USING(syohin_cd)
おお、これなら書く量が少なくて済む。いいね。
USINGだと、括弧の中には、列名しか書けない。結合の両方のテーブルで「同じ列名であることが前提」となる。
同じ列名であっても、型が微妙に違っていたりすると問題が発生するかも知れない。
普通のテーブル設計では、データの紐付けに使用する列は、列名、型とも一致させておくことがセオリーであろう。USINGはそのようなスキーマになっていれば、問題なくUSINGを使うことができる。
USINGでは、条件式で使われる演算子は、=に限定される。BETWEENやら>を使うときは、ONにしないといけない。まぁ、普通の結合では、=しか使わないので、この点については問題ないかと。
外部結合でもUSINGが使えることもある(データベース依存?)。
SQL Server、DB2、AccessではUSINGは使えない。
NATURAL JOIN
長々と説明してきたが、今回紹介したかったのはNATURAL JOINである。NATURAL JOINは「一番新しい結合の方法」かもしれない。
すみません。NATURAL JOINがなかなか出てこないので、ブログのタイトルを少し変えました。
NATUAL JOINを使うと条件式を記述しなくてもよい。結合するテーブル同士で同じ名前の列をすべて等しい条件に自動的になる。
テーブルfooとbarが以下のようにスキーマ定義されていたとする。
CREATE TABLE foo ( a INTEGER, b INTEGER ) CREATE TABLE bar ( a INTEGER, c VARCHAR(20) )
NATURAL JOINすると結合条件は、暗黙的に「foo.a = bar.a」となる。
SELECT * FROM foo NATURAL JOIN bar
NATURAL JOINは、Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLiteで使用できる。
本日は以上。
関連記事
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る
第4版にはNATURAL JOIN載ってます
結合がわからないという初心者の方にはこちらがおススメです。
サイト内を検索
WITH 再帰クエリ その2 [SQLポケリ]
さて、今回もWITH再帰クエリである。
なんとか再帰クエリを書いて、実行させることができたが、なんか「ありがたみ」がない。
なぜかといえば、再帰的にデータを検索しているが、検索するだけでなんの演算もしていないから。今回は再帰ならではの演算をさせてみよう。
ツリー構造には再帰、ということを前回も紹介したが「ツリー構造ならでは」の情報を計算させることにしてみる。表形式のデータは、行と列を指定すれば、一つのセルが決定して、その中に入っているデータを参照できる。
ツリー構造のデータでは、何階層目に位置するデータなのか、といった情報も結構重要であったりする。
1
┣ 2
┃ ┗ 4
┗ 3
例にしている、データは上のようになっていた。
ルートノードとなっている、1のデータは「最初の階層にある」と言って良いと思う。最初を0とするか1とするかの決め事があると思うが、ここでは、最初は0ということにしよう。1の子である、2と3のノードは、階層1になる。2の子である4のノードはさらに下の階層2。
TREE_DATAテーブルの行を見てみると、以下のようになっている。
階層をコメントで記載した。このような結果を計算したいのである。
普通のSELECT命令だけではこのような計算はできない。集計関数を使っても無理かも。ユーザ定義関数ならできるか。
そこで、WITH再帰クエリの登場となる。
初期化ブランチで検索できる行は、すべてルートノードと言って良い。なので、初期化ブランチに引っかかった行は、階層0として良い。
WITH句では、列を決定できるが、計算によって生成されるデータであっても良い。まずは、列LVLを作って、初期化ブランチで0を返してみよう。UNION ALL後の再帰クエリではとりあえず、NULLを戻しておく。
とりあえずは、ルートノードのLVLは0になった。コメントで示した階層に一つ近づいた。
では、次の段階へ進もう。
UNION ALLの後の再帰クエリで、とりあえずNULLとしたところを変更していけば、良いことはなんとなくわかるが、どうしたら良いものか。
TREE_DATAテーブルには、LVLの情報はないので、計算するしかない。tdは、一時テーブルなので、前回の再帰処理の結果がわかるはず。そうか、td.LVLを見ればOKかも?
おっと、全部0になってしまった。
そりゃ、そうか。どっかでインクリメントしないとね。
td.LVL + 1で戻せばOKだろうか。やってみよう。
いいね。
NNO=1はルートノードなので0。
NNO=2と3は、1の子ノードなので、階層は1。OKです。
NNO=4は、1->2->4といった「パス」を経由することになるので、階層は2でOK。2回遷移した(矢印が二つ)。
前回、解説していった「再帰のn回目」みたいなことが、LVLで計算できた!っていうことなんです。
TREE_DATAとtdを結合することで、再帰の前後のデータの両方を参照することができる。というのが、再帰クエリの一番の特徴なのかな。
パスから値を計算する
見事に階層を計算することができた。
最後に、NODE_DATAの合計を計算する再帰クエリを紹介してみたいと思う。
ノード4のNDATA_TOTALに注目して欲しい。計算された値は400となっている。これは、以下の計算式で計算されたものである。
100 + 200 + 100
ノード1 -> ノード2 -> ノード4と再帰のパスを通ってくることになるのだが、その時のNDATAの値を順番に足し算していった結果がNDATA_TOTALとなる。
SUMは、グループの合計を計算する。仮にノード1,2,4と言うグループ分けができれば、SUM集計関数を使用してNDATA_TOTALを計算できなくもない。そんな変なグループ化ができないので、SUM集計関数では計算できないのである。おっと、OracleにはCONNECT BYみたいな文法があるんだっけか?これは要調査か。
再帰の循環
何も考えずに、自分自身を呼び出すと無限ループに陥る、といった話をしたかと思う。WITHの再帰クエリでは、再帰呼び出しできる場所が限定されているので、無限ループしてしまうことが少ないようになっている。
それでも、データの作り方によっては、「再帰の循環」が発生してしまうこともある。
ツリー構造では、ルートから子が生えていって、いずれは子を持たないノードになる。末端のノードは、リーフノードとも呼ばれる。
また、通常は、子ノードが祖先のノードに先祖返りしてしまうこともない。そのようになっていると、タイムリープが発生することになり、親子関係が時系列順に並ばなくなってしまう。なんか、難しい?図にしたら以下のようなことである。
1
┣ 2
┃ ┗ 4
┗ 3
┗ 1
3の子に1がある。3の親も1である。
親ノードへのポインタを持つツリー構造では、こう言ったデータを作成することはできない。上の図は無理やり描いただけ。
と思ったが、TREE_DATAテーブルでNODE_NOがプライマリキーになっていなければ可能か。TREE_DATAテーブルにもその行をプライマリキーを外して追加してみた。
これを先ほどの再帰クエリにかけるとどうなるのか。やってみよう。
エラーになりました。
無限ループになっちゃったわけである。
CYCLE
さて、これを回避する方法もちゃんとあります。
WITH句のオプションでCYCLEというものがある。これを使って循環を検出できるような列を書いておく。CYCLEに続けて、SET なになに、と式を書くがここはあまり重要ではなく、フラグの名前とフラグの値を0/1にします程度のこと。
CYCLEに続けて、再帰の過程で記録しておくべき列を指定する。記録しておいた値が再度出現したら循環とみなし、再帰を停止する。複数であっても良いが、WITH句のパラメータにふくまれている仮想な列を指定する必要がある。
例で言うのなら、TREE_DATAテーブルのNODE_NOは、指定不可で、NNOならOK。
CYCLE 列名 の後のSET LOOP_FLAG TO 1 DEFAULT 0は、循環の検出に使用するフラグの名前と値。
WITHで定義される仮想表に自動的にこの列が追加される。面倒な指定だが省略することはできない。
フラグの値は、数値でなくてもよく、1文字の文字列でも可。SET LOOP_FLAG TO 'Y' DEFAULT 'N'とすることもできる。数値の場合でも桁数が1。
数値、文字のどちらの場合でも、ふたつ指定する値がどちらも同じであってはいけない。SET LOOP_FLAG TO 0 DEFAULT 0はダメ。違いがわからないもんね。
CYCLE指定する列は、例の場合は、NNOが適切。PNOでも循環を検出できるが、以下のように1段階、再帰が深いところまで進んで行われる。
用語や方言について
WITH再帰クエリについて、解説してきた。すべて、Oracle11gで実行して検証している。SQL ServerでもWITHで再帰させることが可能ではあるものの、CYCLEが使えなかったりするので注意が必要。
PostgreSQLでは、WITH RECURSIVE ...と再帰クエリとする場合は、RECURSIVEを明示しないとダメかも。
Oracle11gではRECURSIVE指定はできない。もーまた方言作っちゃって。まぁ、CONNECT BYよりはいいか。
初期化ブランチという用語も「Oracleならでは」なのかも。UNION ALLの前後のSELECT命令をなんと呼ぶかについては結構DBによってバラバラ?
SQL標準だと、「非再帰項」と「再帰項」となっている。非再帰項は最初の初期化の時だけしか評価されないので、名前としては初期化項の方がわかりやすいと思うが。「再帰を含まない初期化クエリ」とでもしておくか。
UNION ALLの前後にどちらを書いても良い、というのが非常に嫌な感じ。説明しにくいじゃないか。
再帰についてはここまで。
サイト内を検索
なんとか再帰クエリを書いて、実行させることができたが、なんか「ありがたみ」がない。
なぜかといえば、再帰的にデータを検索しているが、検索するだけでなんの演算もしていないから。今回は再帰ならではの演算をさせてみよう。
ツリー構造には再帰、ということを前回も紹介したが「ツリー構造ならでは」の情報を計算させることにしてみる。表形式のデータは、行と列を指定すれば、一つのセルが決定して、その中に入っているデータを参照できる。
ツリー構造のデータでは、何階層目に位置するデータなのか、といった情報も結構重要であったりする。
1
┣ 2
┃ ┗ 4
┗ 3
例にしている、データは上のようになっていた。
ルートノードとなっている、1のデータは「最初の階層にある」と言って良いと思う。最初を0とするか1とするかの決め事があると思うが、ここでは、最初は0ということにしよう。1の子である、2と3のノードは、階層1になる。2の子である4のノードはさらに下の階層2。
TREE_DATAテーブルの行を見てみると、以下のようになっている。
SELECT * FROM TREE_DATA NODE_NO PARENT_NO NODE_DATA 階層 --------------------------- 1 NULL 100 -- 0 2 1 200 -- 1 3 1 300 -- 1 4 2 100 -- 2
階層をコメントで記載した。このような結果を計算したいのである。
普通のSELECT命令だけではこのような計算はできない。集計関数を使っても無理かも。ユーザ定義関数ならできるか。
そこで、WITH再帰クエリの登場となる。
初期化ブランチで検索できる行は、すべてルートノードと言って良い。なので、初期化ブランチに引っかかった行は、階層0として良い。
WITH句では、列を決定できるが、計算によって生成されるデータであっても良い。まずは、列LVLを作って、初期化ブランチで0を返してみよう。UNION ALL後の再帰クエリではとりあえず、NULLを戻しておく。
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0 -- LVL 0を戻す
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, NULL -- とりあえずNULL
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA LVL
-------------------------
1 NULL 100 0
2 1 200 NULL
3 1 300 NULL
4 2 100 NULL
とりあえずは、ルートノードのLVLは0になった。コメントで示した階層に一つ近づいた。
では、次の段階へ進もう。
UNION ALLの後の再帰クエリで、とりあえずNULLとしたところを変更していけば、良いことはなんとなくわかるが、どうしたら良いものか。
TREE_DATAテーブルには、LVLの情報はないので、計算するしかない。tdは、一時テーブルなので、前回の再帰処理の結果がわかるはず。そうか、td.LVLを見ればOKかも?
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, td.LVL -- tdのLVLを戻してみる
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA LVL
-------------------------
1 NULL 100 0
2 1 200 0
3 1 300 0
4 2 100 0
おっと、全部0になってしまった。
そりゃ、そうか。どっかでインクリメントしないとね。
td.LVL + 1で戻せばOKだろうか。やってみよう。
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, td.LVL + 1 -- これでどうだ
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA LVL
-------------------------
1 NULL 100 0
2 1 200 1
3 1 300 1
4 2 100 2
いいね。
NNO=1はルートノードなので0。
NNO=2と3は、1の子ノードなので、階層は1。OKです。
NNO=4は、1->2->4といった「パス」を経由することになるので、階層は2でOK。2回遷移した(矢印が二つ)。
前回、解説していった「再帰のn回目」みたいなことが、LVLで計算できた!っていうことなんです。
TREE_DATAとtdを結合することで、再帰の前後のデータの両方を参照することができる。というのが、再帰クエリの一番の特徴なのかな。
パスから値を計算する
見事に階層を計算することができた。
最後に、NODE_DATAの合計を計算する再帰クエリを紹介してみたいと思う。
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL, NDATA_TOTAL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, td.LVL + 1,
TD2.NODE_DATA + td.NDATA_TOTAL
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA LVL NDATA_TOTAL
-----------------------------------
1 NULL 100 0 100
2 1 200 1 300
3 1 300 1 400
4 2 100 2 400
ノード4のNDATA_TOTALに注目して欲しい。計算された値は400となっている。これは、以下の計算式で計算されたものである。
100 + 200 + 100
ノード1 -> ノード2 -> ノード4と再帰のパスを通ってくることになるのだが、その時のNDATAの値を順番に足し算していった結果がNDATA_TOTALとなる。
SUMは、グループの合計を計算する。仮にノード1,2,4と言うグループ分けができれば、SUM集計関数を使用してNDATA_TOTALを計算できなくもない。そんな変なグループ化ができないので、SUM集計関数では計算できないのである。おっと、OracleにはCONNECT BYみたいな文法があるんだっけか?これは要調査か。
再帰の循環
何も考えずに、自分自身を呼び出すと無限ループに陥る、といった話をしたかと思う。WITHの再帰クエリでは、再帰呼び出しできる場所が限定されているので、無限ループしてしまうことが少ないようになっている。
それでも、データの作り方によっては、「再帰の循環」が発生してしまうこともある。
ツリー構造では、ルートから子が生えていって、いずれは子を持たないノードになる。末端のノードは、リーフノードとも呼ばれる。
また、通常は、子ノードが祖先のノードに先祖返りしてしまうこともない。そのようになっていると、タイムリープが発生することになり、親子関係が時系列順に並ばなくなってしまう。なんか、難しい?図にしたら以下のようなことである。
1
┣ 2
┃ ┗ 4
┗ 3
┗ 1
3の子に1がある。3の親も1である。
親ノードへのポインタを持つツリー構造では、こう言ったデータを作成することはできない。上の図は無理やり描いただけ。
と思ったが、TREE_DATAテーブルでNODE_NOがプライマリキーになっていなければ可能か。TREE_DATAテーブルにもその行をプライマリキーを外して追加してみた。
SELECT * FROM TREE_DATA NODE_NO PARENT_NO NODE_DATA --------------------------- 1 NULL 100 2 1 200 3 1 300 4 2 100 1 3 90
これを先ほどの再帰クエリにかけるとどうなるのか。やってみよう。
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL, NDATA_TOTAL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, td.LVL + 1,
TD2.NODE_DATA + td.NDATA_TOTAL
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
SELECT * FROM td
ORA-32044: 再帰的WITH問合せの実行中にサイクルが検出されました
エラーになりました。
無限ループになっちゃったわけである。
CYCLE
さて、これを回避する方法もちゃんとあります。
WITH句のオプションでCYCLEというものがある。これを使って循環を検出できるような列を書いておく。CYCLEに続けて、SET なになに、と式を書くがここはあまり重要ではなく、フラグの名前とフラグの値を0/1にします程度のこと。
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL, NDATA_TOTAL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, td.LVL + 1,
TD2.NODE_DATA + td.NDATA_TOTAL
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
CYCLE NNO SET LOOP_FLAG TO 1 DEFAULT 0 -- CYCLEで循環を検出させる
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA LVL NDATA_TOTAL LOOP_FLAG
---------------------------------------------
1 NULL 100 0 100 0
2 1 200 1 300 0
3 1 300 1 400 0
4 2 100 2 400 0
1 3 90 2 490 1
CYCLEに続けて、再帰の過程で記録しておくべき列を指定する。記録しておいた値が再度出現したら循環とみなし、再帰を停止する。複数であっても良いが、WITH句のパラメータにふくまれている仮想な列を指定する必要がある。
例で言うのなら、TREE_DATAテーブルのNODE_NOは、指定不可で、NNOならOK。
CYCLE 列名 の後のSET LOOP_FLAG TO 1 DEFAULT 0は、循環の検出に使用するフラグの名前と値。
WITHで定義される仮想表に自動的にこの列が追加される。面倒な指定だが省略することはできない。
フラグの値は、数値でなくてもよく、1文字の文字列でも可。SET LOOP_FLAG TO 'Y' DEFAULT 'N'とすることもできる。数値の場合でも桁数が1。
数値、文字のどちらの場合でも、ふたつ指定する値がどちらも同じであってはいけない。SET LOOP_FLAG TO 0 DEFAULT 0はダメ。違いがわからないもんね。
CYCLE指定する列は、例の場合は、NNOが適切。PNOでも循環を検出できるが、以下のように1段階、再帰が深いところまで進んで行われる。
WITH td(NNO, PNO, NDATA, LVL, NDATA_TOTAL) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA, 0, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA, td.LVL + 1,
TD2.NODE_DATA + td.NDATA_TOTAL
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
CYCLE PNO SET LOOP_FLAG TO 1 DEFAULT 0 -- PNOで循環検出
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA LVL NDATA_TOTAL LOOP_FLAG
---------------------------------------------
1 NULL 100 0 100 0
2 1 200 1 300 0
3 1 300 1 400 0
4 2 100 2 400 0
1 3 90 2 490 0
2 1 200 3 690 1
3 1 300 3 790 1
用語や方言について
WITH再帰クエリについて、解説してきた。すべて、Oracle11gで実行して検証している。SQL ServerでもWITHで再帰させることが可能ではあるものの、CYCLEが使えなかったりするので注意が必要。
PostgreSQLでは、WITH RECURSIVE ...と再帰クエリとする場合は、RECURSIVEを明示しないとダメかも。
Oracle11gではRECURSIVE指定はできない。もーまた方言作っちゃって。まぁ、CONNECT BYよりはいいか。
初期化ブランチという用語も「Oracleならでは」なのかも。UNION ALLの前後のSELECT命令をなんと呼ぶかについては結構DBによってバラバラ?
SQL標準だと、「非再帰項」と「再帰項」となっている。非再帰項は最初の初期化の時だけしか評価されないので、名前としては初期化項の方がわかりやすいと思うが。「再帰を含まない初期化クエリ」とでもしておくか。
UNION ALLの前後にどちらを書いても良い、というのが非常に嫌な感じ。説明しにくいじゃないか。
再帰についてはここまで。
関連記事
WITH 再帰クエリー
WITH 再帰クエリ その2
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る
WITH 再帰クエリー
WITH 再帰クエリ その2
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る
サイト内を検索
WITH 再帰クエリ SQLポケリ [SQLポケリ]
前回は、WITH句と再帰クエリについて紹介した。今回は、その続きである。
再帰処理とツリー構造
再帰処理は、ツリー構造のデータ構造を扱う際に、よく使用される。XMLの要素はツリー構造になっている。各要素をくまなく回ってみていく際に、再帰処理を使うと簡単に書けたりする。
SQLでは表形式のデータを扱うことが多いので、再帰処理はあまり得意ではない。SELECT命令にしても、ループ処理をするための制御命令を便利にしただけという印象。
最近拡張された、WITHによって「再帰クエリ」が可能になった、というわけである。
表形式のデータでもツリー構造にすることができる。簡単に実装する方法に、親へのポインタを持つ方法がある。C
言語ならポインタとなるが、テーブルなら行番号を持たせれば良いであろう。テーブルを作成するとしたら、以下のようになる。
図にしたら以下のような感じ。
1
┣ 2
┃ ┗ 4
┗ 3
NODE_NO=1の行には親が存在しない。従って、PARENT_NOの列はNULLとなっている。
NODE_NO=1の行には、子のノードとして、NODE_NO=2と3の二つがぶら下がっている。PARENT_NOの列がどちらも1になっている。
NODE_NO=2の行には、子ノードNODE_NO=4がある。
NODE_NO=3と4の行には、子ノードが存在しない。
PARENT_NOがNULLである行は、子ノードを持たない、いわゆるルートノードである。これは以下のようなSELECT命令で取得できる。
ルートノードは、NODE_NO=1の行が一つだけということがわかる。
ノード1の子ノードを列挙しなさい、と言われたら、以下のSELECT命令で取得できる。
NODE_NO=2と3の二つの子ノードがある。
さらに、ノード2の子ノードを列挙するなら以下とすればOK
そんなに難しくない。
ノード3なら以下。
ノード3には子ノードが存在しないので、結果は空となる。
これらのSELECT命令を順に実行できれば、ツリー構造を「舐めた」と言えるのであるが、PARENT_NO=1とか、2とかの条件はツリー構造の図から人力で拾ってきた。ここをSELECT命令でなんとか書きたいっていうのが再帰クエリの主な目的。
WITHを使うとできるようになっちゃうのだが、この書き方がちょっと慣れが必要。
まず、WITH内のSELECT命令に、UNION ALLが必要。それに、初期化ブランチというものが必要であることは、前でも述べた。
初期化ブランチというのは、初期化を行うためのクエリで、「ツリー構造を舐める」クエリの場合、ルートノードを見つけるというのが初期化ブランチになる。ブランチ、と呼んでいるが、UNION ALLで繋げたクエリのどちらか、と考えるとスッキリするかも知れない。
初期化ブランチでは、再帰呼び出しをしてはいけない。再帰呼び出しをすると無限ループになるからね。
前記事でのWITH再帰クエリをもう一度見てみよう。
エラーとなってしまうのは、UNION ALLで繋げた両方のクエリで再帰呼び出しになってしまっているから。以下のように変更して実行してみると、エラーの様子が変化する。
しかし、これでもエラーになってしまっている。「サイクルが検出」というのは、無限ループに陥ってますよ、と言うこと。UNION ALLで繋げた後の方のクエリで再帰している。
ここの再帰の様子を変更すれば、実行可能な再帰クエリとなる。TREE_DATAの例でやってみよう。
UNION ALLの前のクエリは、初期化ブランチである。切り出してよく見てみよう。
PARENT_NOがNULLである、ルートノードを取り出すためのクエリである。再帰となっていないため、単独で実行できる。
以下は、UNION ALLの後のクエリである。
tdは、WITHで定義したインラインビューである。自分を再帰的に呼び出している部分でもある。そのtdとTREE_DATAを結合している。TD2はTREE_DATAに付けた別名である。
tdを定義中の一部分であるため、取り出して単独で実行することはできない。
tdの定義で、列名を指定している。そのため、tdは以下の列を持っているようになる。
NNO
PNO
NDATA
仮想的な表、tdとTREE_DATAテーブルを結合している。tdの元は、TREE_DATAテーブルなので、自己結合しているようなものだが、単純に一つの同じテーブルを横に並べただけではなく、「再帰呼び出しで得られた結果のテーブルを結合」している感じになる。
結合条件が、td.NNO = TD2.PARENT_NOとなっていることが最大のポイントなわけである。
なんとなくわかってきたと思うが、まだしっかり把握できたわけではないと思うので、再帰処理を順を追ってみていくことにしよう。
再帰の1回目
WITH句の外で、tdを参照する。その最初の参照で、どうなるかというと、初期化ブランチだけの実行結果が一時表に格納される。初期化ブランチは以下のようになっていた。
NODE_NO=1だけの行が一時表に格納される。初期化だからなんとなく納得頂けるのではないかと思う。
再帰の2回目
で、この一時表の結果をさらに、WITH内のクエリにかけるのである。この時、tdの内容が仮に、一時表のものとなる。
td.NNO、td.PNO、td.NDATAは、参考情報である。クエリで取得していないため、戻されることはない。
UNION ALLの後のクエリでPARENT_NO=1となっている行が結合条件に引っかかり、NNO=2と3の二つの行が増えている。一時表には、増えた分の行だけが追加されていくことになる。UNION ALLだからと言って、重複して結果が戻されることはない。
再帰の3回目
前回の呼び出しと、今回の呼び出しで、行が増えている限り、再帰呼び出しが継続する。3回目の再帰処理も行われる。
NNO=4の行が増えた。
増えたので、4回目の再帰も行われる。
再帰の4回目
3回目でNNO=4の行が増えたが、PARENT_NO=4である行が存在しないので、結果として行が増えなかった。そのため、再帰呼び出しは、4回目で終了となる。
わかって頂けたであろうか。
これが、再帰クエリの基本である。
もう、「こういうパターンで再帰クエリは書くもの」と覚えてしまった方が良いかも知れない。
ポイントとしては、以下のようになる。
再帰クエリ
1 WITH内には、UNION ALLで二つのSELECT命令を書く
2 二つのSELECT命令のうち、一つは初期化ブランチなので、再帰呼び出しをしてはいけない
3 二つのSELECT命令のうち、もう一つは再帰呼び出しをして良いが、呼び出し前の一時表結果と結合する
4 呼び出し前の一時表結果との結合条件は、親子関係を示す「PARENT_NO = NODE_NO」のようなものとなる
しかしながら、得られた結果にどう言った意味があるのか?
少々疑問ではないだろうか。
単に、全レコードを取得できただけ?それならば、SELECT * FROM TREE_DATAで十分では?
はい、このクエリではその通りです。
えー、じゃあ再帰クエリを使う意味って...
大丈夫、再帰の場合は、計算方法が異なる。再帰処理の特徴を使えば、再帰処理ならではの計算ができるようになる。
まぁ、急ぐこともあるまい。次回に期待?して欲しい。
サイト内を検索
再帰処理とツリー構造
再帰処理は、ツリー構造のデータ構造を扱う際に、よく使用される。XMLの要素はツリー構造になっている。各要素をくまなく回ってみていく際に、再帰処理を使うと簡単に書けたりする。
SQLでは表形式のデータを扱うことが多いので、再帰処理はあまり得意ではない。SELECT命令にしても、ループ処理をするための制御命令を便利にしただけという印象。
最近拡張された、WITHによって「再帰クエリ」が可能になった、というわけである。
表形式のデータでもツリー構造にすることができる。簡単に実装する方法に、親へのポインタを持つ方法がある。C
言語ならポインタとなるが、テーブルなら行番号を持たせれば良いであろう。テーブルを作成するとしたら、以下のようになる。
CREATE TABLE TREE_DATA ( NODE_NO INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, PARENT_NO INTEGER, NODE_DATA INTEGER ); INSERT INTO TREE_DATA VALUES(1, NULL, 100); INSERT INTO TREE_DATA VALUES(2, 1, 200); INSERT INTO TREE_DATA VALUES(3, 1, 300); INSERT INTO TREE_DATA VALUES(4, 2, 100);
図にしたら以下のような感じ。
1
┣ 2
┃ ┗ 4
┗ 3
NODE_NO=1の行には親が存在しない。従って、PARENT_NOの列はNULLとなっている。
NODE_NO=1の行には、子のノードとして、NODE_NO=2と3の二つがぶら下がっている。PARENT_NOの列がどちらも1になっている。
NODE_NO=2の行には、子ノードNODE_NO=4がある。
NODE_NO=3と4の行には、子ノードが存在しない。
PARENT_NOがNULLである行は、子ノードを持たない、いわゆるルートノードである。これは以下のようなSELECT命令で取得できる。
SELECT * FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL NODE_NO PARENT_NO NODE_DATA ----------------------------- 1 NULL 100
ルートノードは、NODE_NO=1の行が一つだけということがわかる。
ノード1の子ノードを列挙しなさい、と言われたら、以下のSELECT命令で取得できる。
SELECT * FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO = 1 NODE_NO PARENT_NO NODE_DATA ----------------------------- 2 1 200 3 1 300
NODE_NO=2と3の二つの子ノードがある。
さらに、ノード2の子ノードを列挙するなら以下とすればOK
SELECT * FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO = 2 NODE_NO PARENT_NO NODE_DATA ----------------------------- 4 2 100
そんなに難しくない。
ノード3なら以下。
SELECT * FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO = 3 NODE_NO PARENT_NO NODE_DATA -----------------------------
ノード3には子ノードが存在しないので、結果は空となる。
これらのSELECT命令を順に実行できれば、ツリー構造を「舐めた」と言えるのであるが、PARENT_NO=1とか、2とかの条件はツリー構造の図から人力で拾ってきた。ここをSELECT命令でなんとか書きたいっていうのが再帰クエリの主な目的。
WITHを使うとできるようになっちゃうのだが、この書き方がちょっと慣れが必要。
まず、WITH内のSELECT命令に、UNION ALLが必要。それに、初期化ブランチというものが必要であることは、前でも述べた。
初期化ブランチというのは、初期化を行うためのクエリで、「ツリー構造を舐める」クエリの場合、ルートノードを見つけるというのが初期化ブランチになる。ブランチ、と呼んでいるが、UNION ALLで繋げたクエリのどちらか、と考えるとスッキリするかも知れない。
初期化ブランチでは、再帰呼び出しをしてはいけない。再帰呼び出しをすると無限ループになるからね。
前記事でのWITH再帰クエリをもう一度見てみよう。
WITH vfoo(a) AS ( SELECT a FROM vfoo UNION ALL SELECT a FROM vfoo ) SELECT * FROM vfoo ORA-32043: 再帰的WITH句には初期化ブランチが必要です
エラーとなってしまうのは、UNION ALLで繋げた両方のクエリで再帰呼び出しになってしまっているから。以下のように変更して実行してみると、エラーの様子が変化する。
WITH vfoo(a) AS ( SELECT a FROM foo WHERE a = 'A' -- 再帰しない UNION ALL SELECT a FROM vfoo ) SELECT * FROM vfoo ORA-32044: 再帰的WITH問合せの実行中にサイクルが検出されました
しかし、これでもエラーになってしまっている。「サイクルが検出」というのは、無限ループに陥ってますよ、と言うこと。UNION ALLで繋げた後の方のクエリで再帰している。
ここの再帰の様子を変更すれば、実行可能な再帰クエリとなる。TREE_DATAの例でやってみよう。
WITH td(NNO, PNO, NDATA) AS (
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
)
SELECT * FROM td
NNO PNO NDATA
-----------------
1 NULL 100
2 1 200
3 1 300
4 2 100
UNION ALLの前のクエリは、初期化ブランチである。切り出してよく見てみよう。
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
PARENT_NOがNULLである、ルートノードを取り出すためのクエリである。再帰となっていないため、単独で実行できる。
以下は、UNION ALLの後のクエリである。
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
tdは、WITHで定義したインラインビューである。自分を再帰的に呼び出している部分でもある。そのtdとTREE_DATAを結合している。TD2はTREE_DATAに付けた別名である。
tdを定義中の一部分であるため、取り出して単独で実行することはできない。
tdの定義で、列名を指定している。そのため、tdは以下の列を持っているようになる。
NNO
PNO
NDATA
仮想的な表、tdとTREE_DATAテーブルを結合している。tdの元は、TREE_DATAテーブルなので、自己結合しているようなものだが、単純に一つの同じテーブルを横に並べただけではなく、「再帰呼び出しで得られた結果のテーブルを結合」している感じになる。
結合条件が、td.NNO = TD2.PARENT_NOとなっていることが最大のポイントなわけである。
なんとなくわかってきたと思うが、まだしっかり把握できたわけではないと思うので、再帰処理を順を追ってみていくことにしよう。
再帰の1回目
WITH句の外で、tdを参照する。その最初の参照で、どうなるかというと、初期化ブランチだけの実行結果が一時表に格納される。初期化ブランチは以下のようになっていた。
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
NNO PNO NDATA
-----------------
1 NULL 100
NODE_NO=1だけの行が一時表に格納される。初期化だからなんとなく納得頂けるのではないかと思う。
再帰の2回目
で、この一時表の結果をさらに、WITH内のクエリにかけるのである。この時、tdの内容が仮に、一時表のものとなる。
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2 -- tdの内容は再帰の1回目の実行結果となる
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
NNO PNO NDATA td.NNO td.PNO td.NDATA
-----------------
1 NULL 100 -- 初期化ブランチで得られる
2 1 200 1 NULL 100
3 1 300 1 NULL 100
td.NNO、td.PNO、td.NDATAは、参考情報である。クエリで取得していないため、戻されることはない。
UNION ALLの後のクエリでPARENT_NO=1となっている行が結合条件に引っかかり、NNO=2と3の二つの行が増えている。一時表には、増えた分の行だけが追加されていくことになる。UNION ALLだからと言って、重複して結果が戻されることはない。
再帰の3回目
前回の呼び出しと、今回の呼び出しで、行が増えている限り、再帰呼び出しが継続する。3回目の再帰処理も行われる。
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2 -- tdの内容は再帰の2回目の実行結果となる
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
NNO PNO NDATA td.NNO td.PNO td.NDATA
-----------------
1 NULL 100 -- 初期化ブランチで得られる
2 1 200 1 NULL 100 -- 2回目の実行で得られる
3 1 300 1 NULL 100 -- 2回目の実行で得られる
4 2 100 2 1 200
NNO=4の行が増えた。
増えたので、4回目の再帰も行われる。
再帰の4回目
SELECT NODE_NO, PARENT_NO, NODE_DATA
FROM TREE_DATA WHERE PARENT_NO IS NULL
UNION ALL
SELECT TD2.NODE_NO, TD2.PARENT_NO, TD2.NODE_DATA
FROM td INNER JOIN TREE_DATA TD2 -- tdの内容は再帰の3回目の実行結果となる
ON td.NNO = TD2.PARENT_NO
NNO PNO NDATA td.NNO td.PNO td.NDATA
-----------------
1 NULL 100 -- 初期化ブランチで得られる
2 1 200 1 NULL 100 -- 2回目の実行で得られる
3 1 300 1 NULL 100 -- 2回目の実行で得られる
4 2 100 2 1 200 -- 3回目の実行で得られる
3回目でNNO=4の行が増えたが、PARENT_NO=4である行が存在しないので、結果として行が増えなかった。そのため、再帰呼び出しは、4回目で終了となる。
わかって頂けたであろうか。
これが、再帰クエリの基本である。
もう、「こういうパターンで再帰クエリは書くもの」と覚えてしまった方が良いかも知れない。
ポイントとしては、以下のようになる。
再帰クエリ
1 WITH内には、UNION ALLで二つのSELECT命令を書く
2 二つのSELECT命令のうち、一つは初期化ブランチなので、再帰呼び出しをしてはいけない
3 二つのSELECT命令のうち、もう一つは再帰呼び出しをして良いが、呼び出し前の一時表結果と結合する
4 呼び出し前の一時表結果との結合条件は、親子関係を示す「PARENT_NO = NODE_NO」のようなものとなる
しかしながら、得られた結果にどう言った意味があるのか?
少々疑問ではないだろうか。
単に、全レコードを取得できただけ?それならば、SELECT * FROM TREE_DATAで十分では?
はい、このクエリではその通りです。
えー、じゃあ再帰クエリを使う意味って...
大丈夫、再帰の場合は、計算方法が異なる。再帰処理の特徴を使えば、再帰処理ならではの計算ができるようになる。
まぁ、急ぐこともあるまい。次回に期待?して欲しい。
サイト内を検索
SQL WITH句 再帰クエリー RECURSIVE SQLポケリ [SQLポケリ]
最近、SQLネタをブログにアップしている。本日もSQLネタである。
少し前から、WITH句というものが使えるようになっている。
Oracleだと9iから使えるのか。割と昔からあるじゃない。SQLポケリには載っていない。
(改訂第4版には載ってます)。
WITHを使うと、長ったらしいサブクエリを何回も書かなくてよくなる。
これは便利。
CREATE VIEWをSELECT命令内でやってしまうようなもの。
具体例を示しながら解説してみる。
といったSELECT命令をサブクエリで何回も使いたいとする。
ビューを定義してしまえば、話は簡単。
vfoobarという名前のビューを定義した。
vfoobarをテーブルのように使用できるから、長ったらしいfooとbarをa列で結合して...といったSELECT命令をvfoobarという名前だけで使用できるようになる。
ほらね。
vfoobarのところを、SELECT foo.a, bar.b FROM foo INNER...というSELECT命令に脳内で置換してみてください。
なんだかよくわからない、複雑なクエリになってしまうことがわかる。
WITH句を使えば、こういったことを、ビューを作らないで一気にやってしまうことができる。
なるほど。やっぱりこれは便利。
便利なWITH句ではあるが、本来は「再帰クエリー」というものを想定して作られたものらしい。再帰クエリーとはいったいどういったものなのであろうか。
と偉そうに書いてみたが、再帰という概念は説明するのがけっこう難しい。自分の中に自分があるような感じ。プログラミングの場合、関数の再帰呼び出し、ということをよく耳にするかと思う。関数の再帰呼び出しなら、ある関数の内部処理で、自分自身を「再帰的に」呼び出す、というもの。
よく考えずに、関数の再帰呼び出しを行うと、無限ループに陥ることになる。なぜかというと、自分が自分を呼び出して、さらに呼び出された自分も自分を呼び出すので...
通常の関数は、引数をスタックに積む。無限ループといっても、スタックが足りなくなった時点で異常終了する。また、よく考えられた再帰呼び出しは、ちゃんといつかは終了するようにして作成する。
さて、SQLに戻って再帰クエリーである。
ビューを作成する際に、SELECT命令を記述することになるのだが、そのSELECT命令に定義中のビューを使用することはできない。
なぜなら、そのビューはまだ作成されていないから。
CREATE VIEWでviewxxを作成中に、ビューのSELECT命令でviewxxを使うことはできない。
まぁ、そりゃそうだよね。再帰関数呼び出しで、無限ループに陥ってしまうことと同じ問題である。
試しに、上記のCREATE VIEWをOracleでやってみたら、エラーになった。
SQLエラー: ORA-01731: 循環ビュー定義が検出されました
01731. 00000 - "circular view definition encountered"
へー、「循環ビュー」っていうのか。
ビューでは、エラーになるものの、WITH句では、これが許されているのである。
マジか?無限ループにならないのか?
やってみよう。
えー、そうなの。めんどくさー
また、エラーになってしまった。
UNION ALLが必要?
ふえーん。初期化ブランチとはいったい。
要は、再帰呼び出しで無限ループに陥らないように、ちゃんと中のクエリを定義しなさい、ということ。WITHの中で、自分自身を使っても循環ビューのエラーにはならない。
再帰クエリーにする場合は、列指定が必要。再帰クエリーの中には、自分自身を含めてよいが、UNION ALLと初期化ブランチが必要。というところまでわかった。
本日は、ここまでとする。
改訂第4版SQLポケリには、WITH句、WITH再帰クエリが載ってます。
ですが、WITH RECURSIVEのRECURSIVEを書くとエラーになります、とある。これは間違いではないのだが、SQLiteでの話が抜けている。そもそもSQLiteがWITH RECURSIVEに対応していないことになっている。スミマセン。
整理すると以下のような状況である。
PostgreSQL RECURSIVEを書く必要あり
SQLite RECURSIVEを省略可能
その他 RECURSIVEは書いてはいけない
ということで、訂正は以下のようになる。
77ページ
【誤】
PostgreSQLの場合、再帰クエリーを実行する際には、WITHの後に
RECURSIVEをキーワードを指定する必要があります。他のデータベースでは
RECURSIVEを指定するとエラーになります。
【正】
PostgreSQLの場合、再帰クエリーを実行する際には、WITHの後に
RECURSIVEをキーワードを指定する必要があります。SQLiteでは、RECURSIVE
を省略可能です。他のデータベースではRECURSIVEを指定するとエラーになります。
サイト内を検索
WITH句
少し前から、WITH句というものが使えるようになっている。
Oracleだと9iから使えるのか。割と昔からあるじゃない。SQLポケリには載っていない。
(改訂第4版には載ってます)。
WITHを使うと、長ったらしいサブクエリを何回も書かなくてよくなる。
これは便利。
CREATE VIEWをSELECT命令内でやってしまうようなもの。
具体例を示しながら解説してみる。
SELECT foo.a, bar.b FROM foo INNER JOIN bar ON foo.a = bar.a
といったSELECT命令をサブクエリで何回も使いたいとする。
ビューを定義してしまえば、話は簡単。
CREATE VIEW vfoobar AS SELECT foo.a, bar.b FROM foo INNER JOIN bar ON foo.a = bar.a
vfoobarという名前のビューを定義した。
vfoobarをテーブルのように使用できるから、長ったらしいfooとbarをa列で結合して...といったSELECT命令をvfoobarという名前だけで使用できるようになる。
SELECT * FROM vfoobar WHERE a = (SELECT MIN(a) FROM vfoobar) OR a = (SELECT MAX(a) FROM vfoobar)
ほらね。
vfoobarのところを、SELECT foo.a, bar.b FROM foo INNER...というSELECT命令に脳内で置換してみてください。
なんだかよくわからない、複雑なクエリになってしまうことがわかる。
WITH句を使えば、こういったことを、ビューを作らないで一気にやってしまうことができる。
WITH foobar AS ( SELECT foo.a, bar.b FROM foo INNER JOIN bar ON foo.a = bar.a ) SELECT * FROM foobar WHERE a = (SELECT MIN(a) FROM foobar) OR a = (SELECT MAX(a) FROM foobar)
なるほど。やっぱりこれは便利。
WITH RECURSIVE
便利なWITH句ではあるが、本来は「再帰クエリー」というものを想定して作られたものらしい。再帰クエリーとはいったいどういったものなのであろうか。
と偉そうに書いてみたが、再帰という概念は説明するのがけっこう難しい。自分の中に自分があるような感じ。プログラミングの場合、関数の再帰呼び出し、ということをよく耳にするかと思う。関数の再帰呼び出しなら、ある関数の内部処理で、自分自身を「再帰的に」呼び出す、というもの。
よく考えずに、関数の再帰呼び出しを行うと、無限ループに陥ることになる。なぜかというと、自分が自分を呼び出して、さらに呼び出された自分も自分を呼び出すので...
通常の関数は、引数をスタックに積む。無限ループといっても、スタックが足りなくなった時点で異常終了する。また、よく考えられた再帰呼び出しは、ちゃんといつかは終了するようにして作成する。
さて、SQLに戻って再帰クエリーである。
ビューを作成する際に、SELECT命令を記述することになるのだが、そのSELECT命令に定義中のビューを使用することはできない。
なぜなら、そのビューはまだ作成されていないから。
CREATE VIEWでviewxxを作成中に、ビューのSELECT命令でviewxxを使うことはできない。
CREATE VIEW vfoo AS SELECT * FROM vfoo
まぁ、そりゃそうだよね。再帰関数呼び出しで、無限ループに陥ってしまうことと同じ問題である。
試しに、上記のCREATE VIEWをOracleでやってみたら、エラーになった。
SQLエラー: ORA-01731: 循環ビュー定義が検出されました
01731. 00000 - "circular view definition encountered"
へー、「循環ビュー」っていうのか。
ビューでは、エラーになるものの、WITH句では、これが許されているのである。
マジか?無限ループにならないのか?
やってみよう。
WITH vfoo AS ( SELECT a FROM vfoo ) SELECT * FROM vfoo ORA-32039: 再帰的WITH句には列別名リストが必要です 32039. 00000 - "recursive WITH clause must have column alias list"
えー、そうなの。めんどくさー
WITH vfoo(a) AS ( SELECT a FROM vfoo ) SELECT * FROM vfoo ORA-32040: 再帰的WITH句にはUNION ALL操作を使用する必要があります 32040. 00000 - "recursive WITH clause must use a UNION ALL operation"
また、エラーになってしまった。
UNION ALLが必要?
WITH vfoo(a) AS ( SELECT a FROM vfoo UNION ALL SELECT a FROM vfoo ) SELECT * FROM vfoo ORA-32043: 再帰的WITH句には初期化ブランチが必要です 32043. 00000 - "recursive WITH clause needs an initialization branch"
ふえーん。初期化ブランチとはいったい。
要は、再帰呼び出しで無限ループに陥らないように、ちゃんと中のクエリを定義しなさい、ということ。WITHの中で、自分自身を使っても循環ビューのエラーにはならない。
再帰クエリーにする場合は、列指定が必要。再帰クエリーの中には、自分自身を含めてよいが、UNION ALLと初期化ブランチが必要。というところまでわかった。
本日は、ここまでとする。
改訂第4版SQLポケリには、WITH句、WITH再帰クエリが載ってます。
ですが、WITH RECURSIVEのRECURSIVEを書くとエラーになります、とある。これは間違いではないのだが、SQLiteでの話が抜けている。そもそもSQLiteがWITH RECURSIVEに対応していないことになっている。スミマセン。
整理すると以下のような状況である。
PostgreSQL RECURSIVEを書く必要あり
SQLite RECURSIVEを省略可能
その他 RECURSIVEは書いてはいけない
ということで、訂正は以下のようになる。
77ページ
【誤】
PostgreSQLの場合、再帰クエリーを実行する際には、WITHの後に
RECURSIVEをキーワードを指定する必要があります。他のデータベースでは
RECURSIVEを指定するとエラーになります。
【正】
PostgreSQLの場合、再帰クエリーを実行する際には、WITHの後に
RECURSIVEをキーワードを指定する必要があります。SQLiteでは、RECURSIVE
を省略可能です。他のデータベースではRECURSIVEを指定するとエラーになります。
関連記事
WITH 再帰クエリー
WITH 再帰クエリ その2
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
第4版は電子版もあります。
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
WITH 再帰クエリー
WITH 再帰クエリ その2
CROSS APPLY (LATERAL) で関数とJOIN(結合)して見る
SQLポケットリファレンスの歴史
SQLポケットリファレンスの歴史その2
SQLポケットリファレンスが第4版になりました
第4版は電子版もあります。
改訂第4版 SQLポケットリファレンス電子版
サイト内を検索
Copyright Atsushi Asai Google+朝井淳
![[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus) [データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51YR52dRIQL._SL160_.jpg)
[データベースの気持ちがわかる]SQLはじめの一歩 (WEB+DB PRESS plus)
- 作者: 朝井 淳
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2015/03/03
- メディア: 単行本(ソフトカバー)

Access クエリ 徹底活用ガイド ~仕事の現場で即使える
- 作者: 朝井 淳
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2018/05/25
- メディア: 大型本
![[改訂第4版]SQLポケットリファレンス [改訂第4版]SQLポケットリファレンス](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/518GTfGD0aL._SL160_.jpg)


![[改訂第4版]SQLポケットリファレンス [改訂第4版]SQLポケットリファレンス](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51T1BV7VWXL._SL160_.jpg)


